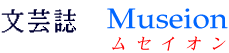
最終更新日 2023年12月12日
|
SF・ファンタジーを読む 時代を超え、地球を飛び出し、未知の生物に出会う。 SF・ファンタジーの世界ではさまざまなシチュエーションで、奇想天外なストーリーが繰り広げられる。 ムセイオンでは、国内外の少々クセのあるSF・ファンタジー作品を採り上げ、その作品がもつ魅力を探っていきたい。 なお、小誌内に別に「ヒューゴー賞を読む」ページを設けている関係上、このページではヒューゴー賞受賞作品は原則的に採り上げない。 | |
|
最新アップ状況 《イングラハム、リーア・ピートリ。女性。年齢:35。身長:2.1メートル。体重:59キロ。死亡状態で到着。クリジウム救急ターミナル。死因:他殺。近親者:不明》 モルグに運ばれてきた死体を前にして、係員がレポートから必要な事柄を書き写す。しかし、その係員は一つだけ書き写し間違えた。それは死体の性別だ。レポートには死体の性別は書かれていなかったのだ。では、なぜ係員は間違ったのか。その死体が“バービー”だったからだ。 “統一教”。90年前に創立されたこの宗派では、男も女も教団に入ると、名前はもちろん個性まですべて抹殺する。そして形態改造手術を施すことで外見も同じにするため、彼らはいつしか20〜21世紀初頭にかけて人気のあった人形の名前から“バービー”と呼ばれるようになっていた。彼女たちは訪れる先々で迫害を受け、60年前にこの月<ルナ>に移住してきたのだった。 バービー殺人事件の捜査に当たることになったのはアンナ=ルイーズ・バッハ警部補だった。彼女は早速バービーの居留地に出向き聞き込みを開始するが、有力な証拠をまったく見出すことができない。バービーたちは一人称を用いず「私たち」と話すため、どの証言も信用にたるものはないのだ。彼女は肌や瞳の色、体毛、指紋など差異が認められるものはすべて排除し、腰に記された識別番号以外はそっくり同じ外見をもつバービーたちの中から、犯人を見つけることなどできないのではと思ってしまうのだった。 その後、捜査が遅々として進まぬ中、まるでバッハたちを嘲笑うかのようにまたバービーが一人殺される。しかも今度はバッハたちの目の前で起きたのだった。バッハたちは必死になって犯人を追うが、犯人にバービーの群衆に紛れ込まれ、また取り逃がしてしまう。…。 SFとしてもミステリとしても十二分に楽しめる作品。他の作家では味わえない独特の雰囲気がヴァーリイの作品にはあって、私のお気に入りの作家の一人でもある。 (創元推理文庫『バービーはなぜ殺される』所収) (2005.10.9/B) | |
|
| |
|
シオドア・スタージョン「英雄コステロ氏」 宇宙船の事務長を務める私が、惑星ボリンケンに向かう船内でコステロ氏と話す機会を持ったのはつい先日のこと。かつて地球で三執政の一人として活躍した大人物、コステロ氏と話ができるというのはそれまで予想もしなかったことで、私にとって大変名誉なことだった。またコステロ氏も、会話をするうちにボリンケンの地理や実情について詳しい私に興味を持ったようで、別れる際には「きみが(ボリンケンに)寄港したときはどんなに忙しくても、かならず時間の都合をつける」と話してくれたほどだった。 ボリンケンは気候や引力、自然の生態などあらゆる面で地球とそっくりな惑星で、これほどまで地球と似ている惑星は六つしか知られていない。そんなボリンケンだったが、私が所定の周航コースを回ってふたたびこの地に足を踏み入れた時には、以前の様子が思い起こせないほど急変してしまっていた。街は荒廃し、通りの至る所で『独りぽっちになってはいけない!…』の垂れ幕を眼にする。これまでの美しく自由に満ちあふれた雰囲気が微塵も感じられない。私にはこの変わり様がまったく理解できなかった。 そんな中、次の日の朝にある人が私を迎えに来る。コステロ氏だった。彼は私に、自分の仕事を手伝って欲しいと持ち寄り…。 地球ではない他の惑星での話であり、その点で間違いなくSF作品なのだろうが、「理系SF」ではないと言えるだろうか、理系の脳をほとんど持ち合わせていない超文系の私にとって、スタージョンの作品には「しっくりくる」ものが多い。言葉でどう表現すればよいか分からないが、どこか「人間的(有機的?)」なものを感じる。ブックレビューで表現ベタは致命的だが、この良さ、実際にもう読んでいただくしかない。 (ハヤカワ・SF・シリーズ『奇妙な触合い』所収) (2003.10.15/B) | |
|
| |
|
シオドア・スタージョン「嫉妬深い幽霊」 街で出会った若い女性にすっかり魅せられてしまったガスは、その3カ月後にビアガーデンで偶然彼女を見かけ声をかける。“この間、街で会った時にどうしておれの頬をいきなりたたいたのか”。そう聞いた彼に、彼女は「お願いよ。本当にごめんなさい」と答えるばかり。前と同じようにビアガーデンからも逃げるようにいなくなってしまった彼女を見て、“きっと何かのトラブルに巻き込まれているのに違いない”と思ったガスは、友達で精神分析医をしているヘンリーに相談することに。すると、意外にもヘンリーはその女性を知っているという。彼の患者だったという彼女(アイオラというのが彼女の名前)の住所を教えてもらったガスは、彼女の部屋を訪れる。 “何かトラブルでも抱えているか”と聞くガスに、アイオラは長い間黙ったままだったが、彼の真摯ぶりについに重い口を開く。彼女と仲良くなった男はみんなさまざまなトラブルに巻き込まれてしまうのだ。そうこうするうちに、ガスの身にも変なことが起こるようになり…。 ファンタジー要素が入った、軽いタッチの掌編。オチ一発の話だが、少しひねくれている所がいかにもスタージョンっぽい。 (ソノラマ文庫海外シリーズ『影よ、影よ、影の国』所収) (2004.3.15/B) | |
|
| |
|
フィリップ・K・ディック「ジョーンズの世界」 1954年刊行。フィリップ・K・ディックの長編二作目。フィリップ・K・ディックは1928年シカゴに生まれ、カルフォルニア大学卒業後、1952年にSF作家としてデビュー。1982年死去。フィリップ・K・ディックは五回の結婚をくり返し、二回の自殺未遂を試み、麻薬中毒にかなり悩まされた人です。双児の兄としてうまれたディックにとって双児の妹が生後一年で亡くなったことがかなり彼のアイデンティティーに繋がったようです。 この作品はディックの作品中でよくある夫婦崩壊寸前ものです。主人公が妻のことが理解できないでいると、知らぬ間に妻が主人公の敵方の人間になっているという例のパターンが繰り広げられるのです。何はさておき、この作品はディックの作品には珍しく登場人物の行動が全員分かりやすく描かれているところがいいです。すごく面白い作品です。 (創元SF文庫『ジョーンズの世界』所収) (2003.12.1/A) | |
|
| |
|
星新一「ボッコちゃん」 バーのマスターがロボットをつくった。女のロボットだ。本物そっくりの肌ざわりで、見わけがつかないほど精巧なできばえ。あらゆる美人の要素を取り入れた完全な美人ロボットだった。 ロボットの仕事はお酒を飲むこと。見た目に力を入れたので、頭はほとんど空っぽ。簡単な受け答えしかできなかった。 「名前は」「ボッコちゃん」 「としは」「まだ若いのよ」 「いくつなんだい」「まだ若いのよ」 「だからさ…」「まだ若いのよ」 美人で若く、しっかりしている。お世辞も言わないし、飲んでも乱れない。 そうしたボッコちゃんの評判は徐々に広まり、店に立ち寄る客が増えていった。 その客の中にひとりの青年がいた。彼はボッコちゃんに熱を上げ通い詰めたはいいが、金に困って、挙げ句の果てには父に怒られるはめになってしまった。 父にひどくお灸をすえられ、今夜限りと店にやってきた青年は…。 あくまでもクールなボッコちゃん。ストーリー自体もとてもクールで読みやすい。 (新潮社『星新一ショートショート1001-1(1961〜1968)』所収) (2006.8.25/B) | |
|
| |
|
三橋一夫「分身」 慶安4年のある日の夜更け。津軽藩主九段十平次と友人の小田切澄人の2人がほろ酔い気分で雪の積もる道を歩いていると、一人の美しい娘とすれ違う。 娘にも聞こえる声で「美人だ」とつぶやく澄人のそばで、眼光鋭い十平次には、娘の後首すじの辺りから蜘蛛の糸のようなものが長くつづいているのが見えた。 妖怪? 十平次は抜く手もみせずに娘を切りつけ、娘はあっけなく死んでしまう。かわいそうに思った澄人は、大樹のかげの雪をかきわけ、土を掘り、丁寧に埋めてあげた。 その夜、澄人が自室で寝ていると、先ほど十平次に斬られて亡くなったはずの娘が現れた。 父より妖術を習い、「分身の法」を使うことができると話す娘。 澄人にお願いがあると言い、澄人はその願いに力を貸すことにしたのだが…。 澄人の娘への思いは、果たして成就するのだろうか。 (高橋書店『忍者小説集 昭和39年11月号』所収) (2023.12.12/B) | |
|
| |
|
クルト・ラスヴィッツ「万能図書館」 友人でもあり編集者でもあるマックス・バーケルは、原稿の催促をするためワルハウゼン教授のもとを訪ねたが、教授は「いいアイデアが浮かばない」と言い、代わりに「既存の文字の組み合わせの数には限りがあるので、ひと文字ひと文字並べ替えた本を網羅して作ったとしても、書物数は無限ではない」という持論をマックスにぶちまける。 ワルハウゼン教授は1冊の本をひとつのテーマは充分に書き尽くせる容量である500ページと仮定し、1冊に必要な文字数を計算。「1ページに40行、1行に50ワードとすると40行×50ワード×500ページ=100万」だと話し、今度は100万字の組み合わせについて考える。アキスペースもひと文字と考えるため、膨大な数になりそうだ。 果たして古今のあらゆる本が揃う総合図書館(万能図書館)を作るにはどれだけの冊数が必要なのか、そしてどれくらいの広さを確保しなければいけないのか。数学者でもある教授が解答を導いていく。 伊藤典夫氏の著者略歴によると、この作品は1901年の作とあるので、100年以上も前に書かれたものだということになる。もし万能図書館が実在するのなら、一度行ってみたい気もする。しかし、お目当ての本を手にするまで途方もない時間がかかるのだろう。 (小尾芙佐訳/早川書房・世界SF全集31『世界のSF(短篇集)古典篇』所収) (2004.9.29/B) | |
|
| |
|
蘭郁二郎「脳波操縦士」 奧伊豆に療養にやってきた私は、村人から変わり者と呼ばれている“森源”と知り合いになった。 当時、暇を持てあましていた私は、時間がある限り外に散歩に出かけ、話し相手を欲していた。そんな時に“森源”と出会ったのだ。それは温室だった。彼が変わり者と呼ばれていることを知らなかったら、もしかすると話しかけていなかったかもしれない。変わり者と呼ばれている理由を知りたいという好奇心が私にはあったのだ。 “森源”と話しているうちに、私はどんどん彼に興味を持つようになっていった。例えば彼の手によってこの温室に設けられた装置は、発明と呼ばれるほど優れており、科学者としての顔ものぞかせる。彼は単なる変わり者ではない。彼の話にすっかり引き込まれてしまった私は、初対面にもかかわらず、すっかり話し込んでしまったのだった。 そして、地球磁力を肥料にして植物を栽培するという彼独自の理論を聞いていたその時、一人の女性が入ってきた。 “濡れたような瞳”、“紅い唇の間からガラスの反射を受けた皓歯”…。彼女はとても美しかった。私は銀座などで見かける美少女たちを見慣れていたが、彼女には“パッと花が咲いたような”美しさがあった。 そんな彼女を、“森源”は「ルミです……」と紹介するだけで、妹とも妻とも言わない。そして気が付くと、ルミはもういなくなっていた。 その後、ルミが私の頭から離れなくなってしまった。そして、私は再び“森源”を訪ねることにした。その時は、まさかルミにそんな秘密があろうとは知らなかったのだが…。 海野十三とともに、戦前の日本SF界を引っ張っていた蘭郁二郎。作品における彼の着眼点には、いつも驚かされる。 (日下三蔵編/ちくま文庫『怪奇探偵小説名作選-7 蘭郁二郎集 魔像』所収) (2005.10.9/B) | |
|
| |
| [ トップページにもどる ] All Rights Reserved Copyright (C) 2004-2023,MUSEION. |
||