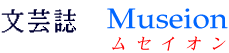
大倉てる子
「黒猫十三」
本庄恒夫と辰馬久は雨の中を夢中で逃げていた。辰馬に誘われて行った場所に警察の手入れがあり、捕まったら大変だと、夜の市街を走りに走ったのだ。途中辰馬とははぐれてしまったものの、最後は命からがら何とか逃げおおせることができた。
しかし、この時間にタクシーはほとんど走っていない。しかもこの大雨。本庄はずぶ濡れになりながら歩いて家に帰らなければならないと腹をくくっていた。
そこへ上手い具合に空のタクシーが一台やってきた。
「乗せてくれ…小山まで、西小山だ」
彼は救われた。だが座席に座ろうとしたその時、何かにつまずいてしまう。ぐにゃりと柔らかいが、弾力のある何かが当たったのだ。車内灯が消えているので鮮明に見えないが、手ざわりからいくと人間のようだった。
「君、ちょいと、電気をつけてくれないか」
「故障なんですよ。すみませんがね」
そこで彼はマッチを擦り、かざしてみた。すると…。
人間だった。若い女だった。しかも触ってみるとぬらぬらとした赤いものがべっとりと掌に付いた。
“死んでいる!”。
足許には死んだ女が転がっている。その傍らには血に染まったずぶ濡れの男。運転手は幸いにもこの状況に気付いていないが、この状況を見たものは、誰もが本庄を殺人犯だと思うに違いない。彼は何とかこの場から逃げ出さなくてはと思った。しかし、どうすればよいというのだ。運転手に気付かれずに逃げる方法などあるものなのか。思い悩んでいると、またあることが起こった。死体がすこし動いたのだ。そう。女は死んでいなかったのだ。
ただ、彼にとって話は少しも好転していなかった。瀕死の重傷を負っている彼女を放って逃げ、その後に彼女が死んでしまったら自分が容疑者にされてしまう。だから、何とか彼女を連れださなければいけない。そして、彼女を介抱して命を取り留めることができれば…。
彼はあるアイデアを思いついた。そして、上手く彼女を連れ出すことに成功した。
さて、本庄は女を自分のアパートに連れてきた。そして、すぐ近くに住んでいる、今年医大を卒業した友人に診てもらおうと友人の家に向かった。ぐっすり寝込んでいた友人を叩き起こし、アパートに戻る二人。しかし、不思議なことが起こった。
彼女が消えていたのだ。アパートのどこを探しても彼女はいない。彼女はどこに行ってしまったのだろうか。
………。
冒頭からの謎の連続には面白みを感じたが、途中から緊迫感がなくなってしまっているのが残念。ただ古さは感じるものの、全体を通しては、これはこれで楽しく読めた。
(春日書房『笑ふ花束』所収)
※大倉てる子の“てる”は、火へんに華。
(2006.7.15/菅井ジエラ)
トップヘ
All Rights Reserved Copyright (C) 2004-2013,MUSEION.