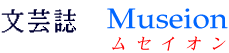ポケミスを読む
第二次世界大戦が終わり、本格的に海外のミステリ作品を紹介しようという気運が高まっていった昭和20年代。海外の作品を読もうとすれば、一部の作品をのぞいて、ほとんどの場合原書にあたらなければならなかった当時の状況のなかで、翻訳ミステリの普及に力を注いでいったのが早川書房のハヤカワポケットミステリシリーズ(通称ポケミス)だった。江戸川乱歩がスーパーバイザー役となり、栄えある第一弾が刊行されたのは1953(昭和28)年9月。2003年で創刊50周年を迎えた。ポケミスの刊行により、1956年の第二回江戸川乱歩賞に早川書房が選ばれていることからもミステリ界におけるその功績は計り知れないものがある。創刊から現在にいたるまで刊行点数は1700点以上。「世界最高最大のミステリ・シリーズ」という謳い文句も納得の充実ぶりだ。
文芸誌ムセイオンでは、101番ミッキー・スピレイン『大いなる殺人』(※)から現在までに刊行された作品を少しずつ紹介していきながら、ポケミスの魅力を伝えていきたい。
(※)1番から100番は当初刊行される予定だったが、結局刊行されなかった。
→これまでの刊行リストを見る

最新アップ状況
NEW! 0157「シルマー家の遺産」エリック・アンブラー(2008.4.21)
目 次
0104「ワイルダー一家の失踪」ハーバート・ブリーン
0138「フランチャイズ事件」ジョセフィン・テイ
0155「ローラ殺人事件」ヴェラ・キャスパリ
0157「シルマー家の遺産」エリック・アンブラー
0163「道化者の死」アラン・グリーン
0336「すばらしき罠」ウイリアム・ピアスン
0360「恐怖のブロードウェイ」デイヴィッド・アリグザンダー
0404「強盗紳士ルパン」モーリス・ルブラン
0421「ペニクロス村殺人事件」モーリス・プロクター
0502「完全主義者」レイン・カウフマン
0582「死は熱いのがお好き」エドガー・ボックス
0634「震える山」ポール・ソマーズ
0643「日曜日は埋葬しない」フレッド・カサック
0646「アデスタを吹く冷たい風」トマス・フラナガン
0697「モルグの女」ジョナサン・ラティマー
0875「第五の墓」ジョナサン・ラティマー
0988「九時から五時までの男」スタンリイ・エリン
1277「黒い霊気」ジョン・スラデック
(準備中)1287「ママは何でも知っている」ジェイムズ・ヤッフェ
1612「三つの迷宮」パコ・イグナシオ・タイボ二世
近日アップ予定
0110「死の接吻」アイラ・レヴィン
0422「一日の悪」トマス・スターリング
0447「トム・ブラウンの死体」グラディス・ミッチェル
0655「生きている痕跡」ハーバート・ブリーン
0688「死亡告示クラブ」ヒュウ・ペンティコースト
0707「檻の中の人間」ジョン・H・ヴァンス
1414「午後の死」シェリイ・スミス
1882「三銃士の息子」カミ
ニューヨークのフリージャーナリスト、レイノルド・フレームは、雑誌の仕事でワイルダーズ・レーンにやってきた。150年ほど前の植民地特有の町並みを復活させようとしているこの町で、「古き良きアメリカ」を取材するためだ。フレームは新聞広告で宿を探し、コンスタンス・ワイルダーが経営する家に2週間ほど間借りすることにしたが、部屋を借りたその日に、その家に住むコンスタンスの妹エレン・ワイルダーが、バスでコラ伯母さんの家に行くと言って出かけたきり行方不明になるという事件が起きる。
コンスタンスらが血相を変えて心配するのとは対照的に、フレームは当初、バスに乗り遅れたりか何かでどこかで待ちぼうけを食らっているのだろうとあまり取りあわなかった。フレームはコンスタンスらの神経質すぎるほどの対応ぶりに面食らってしまうが、程なくそれにはワイルダー家に代々続く呪われた宿命が関係しているということを知る。ワイルダー家がこの町に入植して以来、1775年のジョナサン・ワイルダーを皮切りに、当主がこの町で次々と不可解な失踪を繰り返しているというのだ。エレンやコンスタンスの父であるフレッド・ワイルダーも1年前に失踪している。
フレームは説明がつかないような不可解な現象は少しも信じていなかったが、エレンの失踪事件は、翌日に彼女が撲死体となって墓地で発見されるという無惨な結末で終わりを告げる。
果たして、ワイルダー家の呪われた宿命は今もなお続いているのだろうか? しかし、エレンの失踪は、これまでのどの失踪事件とも趣を異にしている。なぜなら、エレンは「発見」されたからだ。しかも撲死体で。これは明らかに殺人事件なのだ。
ワイルダー家に間借りしたがために、どんどん事件に巻き込まれていくフレーム。そうこうしているのも束の間、今度は食事などの世話をしてくれていたマリー伯母さんが消えてしまい…。
いわゆる「消失もの」だが、カーなどと比べておどろおどろしさはそれほど感じなかった。話の運び方が上手く、アメリカ人が好きそうなエンターテインメント性もあって、なかなか楽しく読むことができた。トリックについてはもう一つという印象を持ったので、ベストミステリの類にはランクインされない作品なのかもしれないが、エンターテインメント小説としては一読に値するものだと思う。
ちなみにこの作品は映画化されているのだろうか?(→ご存知の方がいらっしゃれば、ご一報ください)。先に書いたように、アメリカ人が好きそうな展開もあるので、ハリウッドで映像化してもなかなか面白そうだ。
(2004.12.11/菅井ジエラ)
ブレーヤー・ヘーワード・ベネット法律事務所の所長を務めるロバート・ブレーヤーのもとに、ある日の夕方、奇妙な依頼が舞い込む。それはフランチャイズ家と呼ばれている邸に住むシャープ母娘からのものだった。娘のマリオン・シャープによると、2人はベティー・ケーンという名の女学生を誘拐し、邸に監禁したかどで訴えられているというのだ。当事者のベティーの証言によれば、約1カ月間もの間、邸に軟禁され女中としてこき使われたという。おまけに暴行もされたとも話し、その証拠に彼女の体には傷跡がしっかりと残っていたのだ。しかしシャープ母娘にとっては、まさに寝耳に水の話で潔白を主張していた。
ロバート・ブレーヤーは行きがかり上、この怪事件を調査することにしたのだが、状況は完璧にシャープ母娘が不利だった。
というのも、ベティーは監禁されていた部屋の様子など、訪れたものでなければ分からないようなことを詳しく知っていたからである。
果たして、どちらが嘘を吐いているのか。そして、この事件の背後に隠されていることは何なのか。…。
謎そのものと、裁判が迫るという時間的なスリルが臨場感を出していて面白い。ただ、この作品では知らず識らずのうちに答に近づいていくという手法をとっていて、ロバートの推理のキレが今ひとつなのが、読むものの消化不良を起こしているように思える。
(2007.2.23/菅井ジエラ)
広告会社の美人コピーライターであるローラ・ハントが自宅で殺された。彼女の周りには、8年ほど前からの知り合いで、父親的存在でもある評論家のワルドー・リデッカーや、許婚者のシェルビー・カーペンターなどがいたが、彼女はしばしば少し不可解な行動をとっていた。捜査部長のマーク・マックファーソンは事件解決に乗り出すが、捜査を進めていくうちに、彼もまたローラの魅力に心を奪われていく…。
物語は殺人事件が起こった後の関係者たちによる手記という形で進められるのだが、個人的にはこの形式はちょっと読みづらかった。オーソドックスな書き方でも良かったのではと思う。
この作品は発表された2年後に映画化され、大ヒットしたという。ストーリーに(今では、それはないだろうといえるような)意外性もあり、エンターテインメントとしては、このぐらいの展開の方が受けるのだろう。
(2007.2.23/菅井ジエラ)
1938年、アミリア・シュナイダー・ジョンスンという名の老婦人が81歳でなくなった。彼女は清貧な暮らしをしていたが、その暮らしぶりとは正反対に、彼女には弟のマーチンが遺した300万ドルもの遺産があった。遺言書は作られていなかったのだが、彼女が住んでいた当時のアメリカ・ペンシルバニアには、血族関係があれば、誰もが遺産をもらう権利があることになっていた。
ここでもし近くに親族がいれば、問題にならなかったのだが、不幸にも誰も親族がいなかった。そのため、この遺産相続は新聞を巻き込んで全国的な関心事となり、遺産管財人の元には、我こそが相続人だと主張する手紙が8000通以上届いた。そしてトラブルが絶えず事件性を帯びるようになったのだった。そんな騒動も戦争が勃発すると、次第に忘れ去られたのだが、戦争が終結すると、また脚光を浴びはじめ、相続人探しが再開されることになった。
そして、この案件を新しく担当することになったのが、ジョージ・ケアリという名の青年法律家だった。
ジョージはこれまでの膨大な資料を整理することから仕事を始めた。クズ同然の資料の山から使えるものを探さなければならない。気の遠くなる仕事を毎日続けた。そして努力の甲斐あって、金脈とも言える資料を見つけだしたジョージは、マリア・コーリンという名のフランス国籍の女性の通訳を引き連れて、ギリシャに飛んだ。………。
ナポレオン戦争時代にまで遡り、存在するかどうかさえ分からない遺産相続人を求めるジョージとマリア。ドラマティックなストーリーが展開するというわけではないが、ジョージの堅実な仕事ぶりは、十分に読み応えがある。
(2008.4.21/菅井ジエラ)
今や全米を席巻する『ふた粒の阿片と一滴の魔液』一座。ジュニア・ワトキンスはエルロイ・シュナイダー、ベーブ・ブルーとで作る喜劇トリオの中心的存在となっている。その彼が興業先であるリゾートホテルの自分の部屋で、こめかみを打ち抜かれて死んでいるところを発見される。これまで舞台上で数え切れないほどの銃弾の餌食になってきた彼だったが、実弾となればもう誰も笑えない。何とも皮肉な最期だ。しかも現場である客室の扉にはカギがかけられ、密室状態。死の真相は謎ばかりだった。
ここで警察を呼び捜査依頼を行えれば良かったが、不幸にも、以前より降り続く雪が勢いを増し、とうとう電話など外部との交信ができなくなってしまう。そこで、元警察官のジョン・ヒューゴーと、彼の義理の叔父でホテル総支配人を務めるアーサー・ハッチが事件の真相を探ろうとするのだが…。
この作品で特筆すべきなのは、全体を通して展開される著者のユーモア感覚。映像的に見せていく手法と、言葉の端々に感じられるユニークなキャラクター設計は、他の作家の作品ではあまり見かけられない。おまけに、外部との交信が断たれ孤立してしまったホテル、密室の殺人、そして数多くの関係者たちなど、謎解きの要素が揃っており、ミステリファンでも十分楽しめる作品に仕上がっている。
(2006.2.16/菅井ジエラ)
フリーランスライターのヴァンス・ウエストフォールは、ある雑誌に30日間失踪し、警察の手から逃れてみせるという企画を提出し、成功報酬として1500ドルと雑誌への記事の連載を約束させた。そして失踪後、成功まであと一日というときに自分の部屋に帰ってみると、身に覚えのないところから封書が来ていた。それはある信用相互銀行の支払い明細書で、その明細書によるとなぜか年末の二週間、そこで働いたことになっている。その銀行は失踪劇を演じる前に当座の資金として300ドル借りに行ったところだったので、何かの間違いだと思い、以前会った担当者に再度会ったが彼らの態度はみなどこかおかしい。ウエストフォールはその銀行訪問を機に、にわかには信じられない「すばらしき罠」にかかっていくのだった。
文字通り絶体絶命に陥った彼は、機転を利かせて真の犯人をどんどん追いつめていくが、どれも見事に上手くいってしまうので、「こんなに何でも上手くいくものなのか?」と少し首をかしげたくなるところがある。また、ハードボイルド的要素も一部に感じられるが、バイオレンスというか力業のようなものがないのでどこか物足りない気もする。
ただし、アリバイの一切ないところから見事に立ち直っていく展開は順を追ってしっかりと描かれており、全体としてはよくできた作品だといえる。
※蛇足だが、私が持っている本は129ページから144ページがダブッていて、145ページから160ページが欠けている。というわけで、この15ページの間に何が起こったのかいまいち分からず、その後の展開から推測するしかなかった。できればちゃんとしたものをもう一冊買ってこの部分だけ読みたいが、確かこの本は好評品切れ中だったはず。この本を所蔵の方でどなたかこの部分だけコピーしてもいいという方がいらっしゃればお願いできないだろうか。
(2004.3.3/菅井ジエラ)
最後の凶行からしばらくナリを潜めていた殺人鬼ウォルドウ。
彼からと思われる殺人予告状が『ブロードウェイ・タイムズ』紙の主筆、バート・ハーディンのもとに送られてきた。
「…水曜日夜半、八時から十二時までのあいだに小生はふたたび行動に訴える。…」
最後の殺人が起こってから10カ月経っていたが、ショーに出演する女性たちを次々に殺害した彼の名は、ブロードウェイだけでなく、広くニューヨーク中に広がっていた。
その彼が今夜の殺人を予告してきたのだ。
バートはロマノ警部と連絡を取り、ウォルドウ逮捕に協力するが、その甲斐なく新たな被害者を生みだす結果となってしまう。
その被害者とは、バートを慕っていた踊り子のアンジェール・ブランだった。彼は彼女にウォルドウ逮捕を誓う。
タイプされた文字の特徴から、バートの会社にあったタイプライターの一つで打たれたことが分かる。となると、犯人はバートの知る身近な人物なのか。……
最後にひとひねりあるが、トリックがどうこうというものではない。ただ、本格ハードボイルドと呼んでも遜色のない仕上がりにはなっているといえる。
(2007.3.29/菅井ジエラ)
場所は大西洋横断定期船『プロヴァンス号』船内。これから何日間も続こうという旅の2日目に無線電信が入る。
《アルセーヌ・ルパン貴下の船中にあり》
電信は彼の特徴を発し続けたが、雷の一撃によって突然途絶えてしまった。
「一等船客、毛髪ブロンド、右前腕に傷あり、単独旅行、姓名はR…」
ルパンがこの船の中にいる。このニュースは瞬く間に広がり、楽しい旅が恐怖の旅へと変貌してしまった。
だが、乗員乗客のうちの一体誰がルパンなのか。
無線電信が伝えた手がかりを照らし合わせ、疑わしい人物を絞り込んだまでは良かったのだが…。
“ルパンの逮捕”という意外な話から始まるアルセーヌ・ルパンシリーズの記念すべき第一短編集。
この短編集には「アルセーヌ・ルパンの逮捕」の他、生来の天才ぶりを物語る「女王の首飾り」など8編が収載されている。
(2007.2.23/菅井ジエラ)
『強盗紳士ルパン』収録作品
「アルセーヌ・ルパンの逮捕」
「獄中のアルセーヌ・ルパン」
「アルセーヌ・ルパンの脱走」
「謎の旅行者」
「女王の首飾り」
「ハートの7」
「さまよう死霊」
「遅かりしシャーロック・ホームズ」
ペニクロス村で、ジェシィ・ベーカーという幼い女の子が何者かによって殺された。
場所は、村の人々が『郭公の森』と呼んでいるところ。ジェシィはそれまで外で遊んでいたが、急にいなくなり、心配になったその子の母親がウッドマン巡査に相談。ウッドマンが森の中で変わり果てたジェシィの姿を発見した。
その村はイギリスのどこにでもありそうな村だったが、1つだけ他の村と違ったところがあった。
それは、この前の年にも殺人事件があったということ。ダフネ・ボーマントという名の幼女が『郭公の森』で何者かに殺されていたのだ。
これで犠牲者は2人目。幼女連続殺人事件となった。
前回、殺人事件が起きた時に捜査にあたったのは、ロンドン警視庁の首席警部の中で一番若いといわれるフィリップ・ハンター。
この時はほとんどお手上げ状態で、何の解決をみることもできなかった。
ハンターはロンドン警視庁警部のダトンとともに、再度、目に見えない犯人を追うことになったのだが…。
著者のモーリス・プロクターは、19年間にわたり警察生活を送っていたことがあるという。
ストーリー展開に派手さはまったくないが、少しずつ着実にすすめるハンターの捜査手法は、そんな著者の警察時代の経験が作りだしたものだろう。
スーパーマンでも何でもないハンターの人間味あふれる姿には逆に好感がもてる。
(2008.3.22/菅井ジエラ)
自分の思い描いていた理想的で落ち着いた生活を手に入れたマーチン・プライヤー。しかし、その幸せな日々も長くは続かず、一通の手紙によってぶち壊されてしまった。なぜなら、その手紙は脅迫状だったからだ。
その内容は、マーチンが妻のグレースを殺す場面をそっくり写真に収めたというものだった。そう、マーチンは理想的な生活を得るために妻を死に追いやっていたのだ。
マーチンは手紙の内容から、脅迫者は彼の少ない友人のなかの誰かに違いないと推測する。
そして脅迫者の候補としてリストアップしたのは5人。できる限り早く脅迫者を探して始末しなければ、彼の前に安穏の日が再びやってくることはない。
かくしてマーチンの脅迫者探しが始まった。
“完全主義者”を自認するマーチンは、脅迫者候補リストの中から一人また一人と候補者を絞り込んでいく。しかし、候補者の一人、サリーに魅かれていくに従って、彼の推理に支障をきたすようになるのだった。
果たして、脅迫者は一体誰なのか。そして脅迫者探しの結末は?
1955年にエドガー賞最優秀処女長編賞に輝いた名作。かつて冷酷無比であったとされるマーチンがサリーに熱を上げていく展開には、少し違和感を覚えなくもないが、全体的にとても良くできていると思う。マーチンも人の子ということなのか。決して読んで損はない作品だ。
(2004.11.26/菅井ジエラ)
元新聞記者で宣伝代理業者のピータ・サージャントは、金持ちの未亡人ヴィアリング夫人からロングアイランド・イーストハムプトンにある彼女の別荘「北砂丘荘」に招待される。ヴィアリング夫人がなぜ自分を招待したのか分からなかったが、この暑い夏を別荘で優雅に過ごすのもいいと考えたピータは、仕事を秘書のフリン嬢に任せてイーストハムプトンに向かう。到着すると、そこには新進気鋭の画家ポール・ブレクストンや彼の妻であり、ヴィアリング夫人の姪でもあるミルドリド・ブレクストン、フレチャ&アリー・クレイポール兄妹、ある新聞で『本のおしゃべり』という書評欄を担当するメアリ・ウェスタン・ラングといった面々が揃っていた。
ある日、みんなで海水浴に出かけた時、ミルドリドが波に呑まれ溺死してしまう。彼女は泳ぎが上手だったので、みんなは「どうして?」と口を揃えていたが、検屍の結果、遺体から睡眠薬が検出されたこと、そして少し前から彼女が神経衰弱にかかっていることが周知の事実になっていたことなどから、警察は彼女の溺死を単なる事故、あるいは睡眠薬を利用した殺人事件という両面で調べることにした。しかし、捜査は遅々として進まない。そんな中、第2の死者が出る。今度は明らかに殺人であった。
記者魂が湧いてきたピータは、独自に調査を行い記事を書いて新聞に売り込もうと決意。そうして自分でこれらの事件(事故?)を調べていくうちに、徐々に別荘に招かれた人たちの複雑な人間関係を知ることになるのであった。
エドガー・ボックスは小説、戯曲、テレビと多才を誇るゴア・ヴィダルの変名。…と書いたが、これは本書裏表紙に書かれてあった文言。恥ずかしながら、私はゴア・ヴィダルについて、『マイラ』『マイロン』の著者であるということぐらいしか知らない。
ただし、この作品が「本職」の推理小説作家が描く良質の作品レベルまで達したものだということだけは私にも言える。本格ミステリ好きの読者にはおすすめの作品だ。
(2004.4.19/菅井ジエラ)
レコード新聞の記者ヒュー・カーティスは、その日、これまでにないというくらい暇な時間を過ごしていた。記事になるネタがない。早く勤務時間が終わればいいのに…。そんな時、夜勤の報道部長のハッチャーからカーティスのもとに指示が入った。
それは、いつも情報を提供してくれるアクスフォード・クロス病院の門番からのネタだった。何者かがミセス・ワードという女に電話をかけ、彼女の父親が自動車事故に遭い呼んでいるから病院に来てほしいと伝えたが、彼女が病院に行ってみると、それは嘘だったというのである。
カーティスは、そんなことはよくある悪戯で、わざわざ彼女に話を聞くまでもないと思っていたが、社内にいてハッチャーにガミガミやられるよりマシと思い、パーマーズ・ロードにある彼女の自宅へと向かった。
家に着くと、彼女が警察に通報したのか、パトカーが1台停まっている。カーティスは警官に職務質問されたので、ここにやってきた経緯を包み隠さずに話すと、それを聞いた警官は血相を変えて彼女の家のドアをたたき出す。終いにはカーティスも駆り出されて一緒にドアに体当たりし、ドアを壊して家の中に入った。
警官が「ランドン!」と大声で叫んでいる。その後カーティスは家の外に閉め出されてしまった。間もなくタクシーがやってきて、1人の女性が降りると、カーティスがその女性に近寄るよりも先に警官が彼女を家の中に押し込んでしまった。
カーティスには、一体何が起こっているのか見当がつかなかったが、彼が受けた印象ではこうだった。
警官はミセス・ワードとランドンという男の2人がどちらも家にいると思っていた。しかし、カーティスの話を聞いて大騒ぎになった。ミセス・ワードは帰ってきたが、ランドンという名の男はいなくなってしまったのだ。
これは記事になる。まだ他の新聞記者は現場に来ていない。これで他紙を出し抜ける。カーティスはそう思っていたが、ランドンという男が何者なのか、まったく分からない。
カーティスは社に戻り、他の記者も総動員でランドンの招待を調べたが、やはりまったく分からなかった。
それが一本の電話が発端となって分かった。
「カーティス、すぐ軍需省へ行ってくれんか。パーマーズ・ロード事件で11時半に記者会見をやるそうだ」
急いで軍需省に向かうカーティス。軍需省の担当官は集まった記者たちに話した。
「…ランドン氏はバッキンガムシャのクリードにある本省研究所で働いている物理学者です」
ランドンは軍需省の中でも、かなり重要な位置にいる物理学者で、そのランドンが失踪してしまったというわけだ。ただ事ではない。そして、その後、また事件が展開した。
ランドンの誘拐者を名乗る犯人から身代金の要求があったのだ。その額、3万ポンド。
その手紙には、身代金と引き替えにランドンを釈放すると書いているのだが…。
1つの誘拐事件にまつわるストーリー展開だが、なかなかしっかりと読ませてくれる。ポール・ソマーズはアンドリュウ・ガーヴの変名。新聞社が舞台の話は、さすがに上手だ。
(2008.3.30/菅井ジエラ)
小説家志望の黒人青年フィリップ・バランスがマルガレータ・ルンダルと出会ったのは、彼がパリのグレバン博物館でガイドのアルバイトをしていた時だった。マルガレータはスウェーデンから大学入学資格試験を受けにパリにやってきていたのだ。
彼女に一目惚れしてしまったフィリップは、住み込みで子どもの世話をする仕事を彼女のために見つけてやり、毎週デートを重ねていた。おまけに、世話をした家の主人ジョルジュ・クールタレスが出版代理人をしており、その縁でフィリップは待望の処女作『日曜日を葬らない』を出版することができるなど、恋に仕事に幸福の絶頂を迎えているかのようであった。
しかし、その幸福も長くは続かない。フィリップはクールタレス夫人から奈落の底に引きずり込まれてしまうような言葉を聞くのだった。……。
生活のすべてを小説(執筆)のために考えるフィリップ。その場その場のシチュエーションを小説に置き換えるとどうなるか。自分ならどのようにストーリーを展開させるか。日々、ここまで考えてこそ、真の小説家になりうるものなのだろうか。
本書は1958年度のフランス推理小説大賞に輝いた作品。フレンチミステリもやっぱり面白い。
(2006.1.22/菅井ジエラ)
15年ほど前にあった解放戦争の際に行方不明になった、大量の銃が密輸されているとの情報を得たテナント少佐は、共和国側からトラックで葡萄酒を運んでいる商人ゴマールが怪しいとにらみ検問をおこなう。しかし結果は惨憺たるもので、証拠となるものは何も出てこない。それでもテナントは「こいつしかありえない」という揺るぎない確信を持っていた。では、この厳重な監視下でどうやって密輸をおこなっているのか。
テナントの推理が冴える表題作をはじめ、中世イタリアを舞台にした歴史密室ミステリ「玉を懐いて罪あり」など、ここに収められたの全部で7編。どれも意外な結末が用意されている。また、最初の4編はテナント少佐が主人公になっているが、彼の人間的魅力も読んでいて心地よい。
この作品は、ポケミス50周年記念「復刊希望読者アンケート」で、5年前の同アンケートに引き続き連続1位に輝いている。
(2003.10.4/菅井ジエラ)
『アデスタを吹く冷たい風』収録作品
「アデスタを吹く冷たい風」
「獅子のたてがみ」
「良心の問題」
「国のしきたり」 「もし君が陪審員なら」
「うまくいつたようだわね」
「玉を懐いて罪あり」
舞台は真夏のシカゴ。モルグ(死体安置所)に収容されていた身元不明の若い女性が一瞬のうちに消えるという事件が起こる。2年前に家出をしたまま行方不明になっている姪を捜して欲しいという依頼を受けた探偵のウィリアム・クレインは、ニューヨークから彼女の身元を調査しにモルグにやってきていたが、女性の遺体が消えたちょうどその時、そこに居合わせたことから警察に疑いの目を向けられることになってしまう。クレインは遺体を隠匿したとして自分を逮捕しようとしている警察に対して疑いを晴らすべく、探偵事務所の仲間とともに調査に乗り出す。
調査を進めるうちに2つのギャングのボスから狙われるようになるクレイン。彼らはクレインと同じく、彼女の身元を知りたがっているらしい。モルグから突然消え去った身元不明の飛びっきりの美女は一体誰なのか。窮地に陥っても持ち前の頭脳と行動力で次々と打開していくクレイン。そして最後には意外な結末が控えているのだった。
ラティマーの作品は展開が早く、中たるみもあまりないので「読み疲れ」しなくていい。最後が少し尻すぼみだったが、全体的には楽しく読むことができた。
(2004.2.28/菅井ジエラ)
新興宗教団体「ソロモンの葡萄園」にいるピネロープという女性を探しだしてほしいという依頼を受けた私立探偵カール・クレーヴェン。彼が南部の田舎町ポールトンに着いたのは、うだるように暑い夏の日だった。先にこの場所に乗り込んで調査にあたっていた相棒のオーク・ジョンスンから重大な情報をつかんだと報告を受けていたため、カールは早速オークの元を訪れたが、そこで目にしたのは便器の前に転がって死んでいるオークの姿だった。悪事の限りを尽くしているという噂の絶えない「ソロモンの葡萄園」。地元の警察ですら踏み込めない聖域から、カールはどのようにして女性を救い出すのか。
街のギャング、警察、そしてとびっきりの美女。軽いタッチのハードボイルドながら、最後もしっかりと締めてくれている。展開が早いので、遅読の私もあっという間に読むことができた。人によって好き嫌いがはっきりする作品だろうが、機会があればぜひ読んでみてほしい。
(2004.2.9/菅井ジエラ)
古くてみすぼらしいビルの一室にあるキースラー商会は、キースラー氏以外には社員のいない小さな会社。ドアには「物品販売業」と書かれている。その日も彼はいつもの時間に家を出て、九時きっかりに、いつもと同じように会社に出勤。社内を整理した後は歯科医院に電話。そして仕事らしき電話を1本入れる。さらに新聞をすみからすみまで読んでいると昼になったので昼食へ。どうやら商売は繁盛していないらしい。昼食を取った後は外出。約束の場所へ向かう。彼が行った先はとある倉庫だった。誰ひとりいない倉庫で、何やら仕事にかかろうとする彼。彼はここでどんな仕事をしようとしているのだろう。
時間にとても正確なキースラー氏も家では印象が悪い。彼の仕事は一体なのか。
彼の奇妙な仕事ぶりを描いた表題作をはじめ、さる協会が推進する計画を実行したために、以前よりも大きな不安をいだくようになった男を描く「ブレッシントン計画」など計10編の短編を収録。短編の名手といわれる「エリン、ここにあり!」の異色短編集だ。
(2003.10.4/菅井ジエラ)
『九時から五時までの男』収録作品
「ブレッシントン計画」
「神さまの思し召し」
「いつまでもねんねえじゃいられない」
「ロバート」
「不当な疑惑」
「運命の日」
「蚤をたずねて」
「七つの大徳」
「九時から五時までの男」
「伜の質問」
降霊術により死者の魂との交信を図る、霊媒師ウェブ夫人主宰の<霊気マンダラ協会>。素人探偵のサッカレイ・フィンがこのインチキくさい協会に参加しようと思ったのは、毎日が退屈で“謎”に飢えていたからだった。しかも幸いにも(?)、この有名人が揃う協会には怪しい謎があった。そしてまた、フィンが参加した降霊会の席では、亡夫モーリスの霊が乗り移ったウェブ夫人の口から驚くべき言葉を聞いたのだった。
「わたしだ、わたし、モーリス・ウェブだ。わたしは殺されたのだ」
その日を境にフィンの周りで不思議な事件が次々と起こる。ロダーデイル博士の密室からの消失、その後の絞殺死。人気歌手スティーヴの空中浮遊、その後の墜落死。この2つの事件には同じエジプトの呪いの護符が関係していた。
一連の超自然現象は本当に起こったことなのか。不可解な死の真相とは。怪しげな独特の雰囲気の中で進行されるフィンの名推理。ディクスン・カーばりの世界が堪能できる本格ミステリ作品だ。
(2003.10.4/菅井ジエラ)
レビュー準備中
(2005.5.22/菅井ジエラ)
『ママは何でも知っている』収録作品
「ママは何でも知っている」
「ママは賭ける」
「ママの春」
「ママが泣いた」
「ママは祈る」
「ママ、アリアを唱う」
「ママと呪いのミンク・コート」
「ママは憶えている」
メキシコシティで私立探偵をしているエクトルの元に、続けざまに3つの依頼が転がり込む。1つは58年前に殺されたとされるメキシコ革命の英雄サパタの所在をつきとめてくれというもの。依頼人曰く、当時殺されたのは彼ではないというのだ。2つめは映画女優からの依頼。娘の様子が最近おかしくて気になるので原因を見つけだしてほしいというもの。そして3つめは鉄鋼会社の工場内で起きた殺人事件の犯人を捜してほしいという会社社長からの依頼だ。
混沌とするメキシコシティの街が、寝食を忘れて調査を続けるエクトルの体力を徐々に奪っていく。一つひとつの事件が複雑に絡み合い、解決の糸口が一向に見つからない。しかし、友人や妹の助けを借りながら根気よく事件の疑問を解消していくうちに、おぼろげながら真相が見えてくるのだった。
物語の舞台となっているメキシコシティの雰囲気が独特で、メキシコ版ハードボイルド(風俗小説)といったところ。内容については、特に中盤以降の展開に無理があり、破綻している感がある。3つの調査を同時進行で行うわけだが、それぞれの事件の解明のされ方も少々お粗末。中盤までは「どうなる?どうなる?」と思いながらページをめくっていたのに…。ちょっと残念。
(2004.3.20/菅井ジエラ)