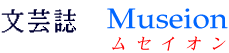
「社長と秘書と社員の毒気
(The Man, the maid and the Miasma)」(1910)
会社を経営するロバート・ファーガソンは、1カ月ほど前に雇い入れたローランド・ビーンなる男を昨日解雇した。ビーンは身のこなしが“中年の聖者”のような、“勤勉と几帳面を説いている本を残らず暗記”しているような男で、他の社員に悪影響を与えると思ったからだ。
そのビーンが夕方早くにファーガソンに電話をよこし、事務室の外で待っていると伝えてきたのである。
「今は忙しいからと言ってくれ」というファーガソンに対し、ビーンは“自由におなりになるまでお待ちいたします”。ファーガソンは事務員がみんな帰った後もビーンのことを考え、一人事務室に残っていた。「どうしてこんなことで困っているのか…それは、読者がビーン君を1カ月雇ったことがないからである」
その後、ファーガソンは意を決して事務室を出ると、そこにはビーンがいた。しかし、彼からこんな言葉をかけられたのだ。「外へはお出になれないと思いますが…この建物は全部閉められてしまいました」。
ビルの門衛がカギを締め、外に出られなくなってしまったのだ。明日の朝にならないとカギは開かない。この後、13時間もこいつと二人きりでいないといけないのかと思うと、それだけでゾッとした気分になるファーガソン。
ファーガソンは逃げるように部屋を飛び出し、暗い階段をかけあがっていくと、左手のドアから淡い光が射すのを見た。もう一人ビルに閉じこめられた人間がいたのだ。しかも、そのドアはファーガソンの顔なじみであるブレイズウェイトという人の事務所だった。ブレイズウェイトとなら長い時間も何とか過ごせそうだ。そう思ったファーガソンはノックもせずにさっとドアを開けた。すると、そこにいたのはブレイズウェイトではなく女性だった。しかも何たる偶然!その女性はファーガソンが1年半前に別れた昔の恋人だったのだ。二人は“別れ際に、もうお互いに口をきかない約束”をした間柄だったのだが…。
妙なところで再会した元恋人二人と、ひたすら毒気づくもうひとりの男。夜のビルに取り残された三人は、この後どのような時間を過ごすのだろうか。
ウッドハウスは劇の台本も数多く手がけているが、この作品は舞台で演じるのにぴったりだという印象を持った。
また冒頭を読んでいると、ジョン・チーヴァーの「ニューヨーク発五時四十八分」を連想してしまった。チーヴァーがこの作品を読んでいたかどうかは分からないが、同様のシチュエーションからどのように話を展開させていくか。短編の名手である二人の異なったレシピを読み比べると、とても興味深い。
★所収本
・田中春美訳/富士書店『ウッドハウス短編集』(社長と秘書と社員の毒気)
(2005.8.27/菅井ジエラ)
「P・G・ウッドハウスを読む」ページトップヘ
「文芸誌ムセイオン」トップヘ
All Rights Reserved Copyright (C) 2004-2016,MUSEION.