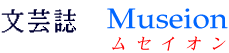
最終更新日 2004年9月4日
|
ヒューゴー賞受賞作品を読む 1953年に創設された世界でも有数のSF賞の呼称で、正式名は「SF功労賞」(Science Fiction Achievement Awards)。 1年に1回アメリカ国内で開かれる世界SF大会(ワールド・コンペティション)参加者の投票によって決められる。 アメリカの名だたるSF作家は、この賞の受賞者リストにずらりと名を連ねるてはいるが、これまで非英語圏のSF作家が受賞した例はなく、そういった意味では、アメリカのSF賞と言ってもいいかもしれない。 →これまでのヒューゴー賞歴代受賞作品リストを見る | |
|
最新アップ状況 ゲンリー・アイは探索ロケットにのって単独で「冬の惑星」にやってきた。ゲンリー・アイがのっていたロケットは不時着して故障してしまったため、近くの宇宙を周回している仲間の宇宙船と連絡をとらなければならない。が、彼は連絡を取る前に、「冬の惑星」について色々と探索するのだった。 ゲンリー・アイが最初に足を踏み入れたカルハイド王国では彼の運命を左右する、アルガーベン王と、王の側近のエストラーベンと出会う。唯一自分が宇宙からやってきた人間であることを理解してくれているエストラーベンの助力もむなしく、ゲンリーはアルガーベン王に理解されずカルハイドから出ていかなけらばならなくなる。又、エストラーベンもゲンリーに加担したことによって罪をかぶり国外追放の身となる。 オルゴレインにやってきたゲンリー・アイは自分が違う惑星の人間で、どのようにしてやってきたのか話せば話すほど理解されずに狂人扱いされ、やがてゲンリー・アイはオルゴレインで罪人扱いされる。なぜなら、「冬の惑星」の人々は古代人のような質素な生活を営んでいて、科学的な考えなど想像を超えたものだったからだ。そして、ゲンリーの言うことが理解されない理由には「冬の惑星」の人々の特徴が原因となっていた。それは、「冬の惑星」の人々が両性具有で、特定の時期以外は生殖機能を有していないのだ。ゲンリーは、理解されない境遇に耐えながら雪原を彷徨い歩き、再会したエストラーベンに力を借りて何としてでも仲間の地球人と連絡を取ろうとするのだった。 この作品の見どころは、男性のゲンリーと両性具有者のエストラーベンが苦難な旅を幾月も共にしている時、二人の間で相互理解が生まれる。それは、性の違い、価値観の違いを超えたものだ。二人のやりとりを読んでいると、ヘテロセクシャルな読者としては異性愛と同性愛の違いとは何なのかということについて考えずにはいられない。 (ハヤカワSF文庫『闇の左手』所収) (2003.12.1/A) | |
|
| |
|
1972年(ショート・ストーリー) ラリイ・ニーヴン「無常の月」 男が夜中にテレビ番組を見ていた時、外がとても明るいことに気づく。こんな明るい月は見たこともない。 「月はさらに明るさを増しているようだ」。男は恋人に電話をする。寝ていたため機嫌が悪かった彼女も、この異常事態に眠っていられない。「あれっきり、寝る気なんかなくなったわ。明るすぎるんだもの」。そして二人は落ち合い、町をうろつきながら、この事態について考える。月の光は太陽の反射。とすると、何かが太陽に起こったとしか考えられない。もしかすると太陽が新星(ノヴァ)化しつつあるということなのか。もしそうだとすれば、炎の衝撃波が町を襲い、人類の大部分が死んでしまうはず。このまま何もできずに、ただ日の出を待つしかないのか。そうこうするうち、これまで見たことのないような雹が降りだし、やがて激しい暴風雨に変わった。これは地球滅亡の前触れなのだろうか。 二人は天候の異変で気が動転しているようだが、反面、彼らの行動を見ていると、誰も一人残らず死んでしまうかもしれないというのに非常に落ち着いているようにも見える。人って案外こんなものなのだろうか。 物語はすごくSFチックだが、そうかといって、こんなことは100%あり得ないと断言できそうにないストーリー設定。「さすがSF作家!さすがラリイ・ニーヴン!」と思ってしまった。 (2003.8.13/B) | |
|
| |
| [ トップページにもどる ] All Rights Reserved Copyright (C) 2003-2014,MUSEION. |
||