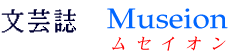
ウィリアム・サンソム「垂直な梯子」
“なんだってこんなことを、自分から買ってでてしまったのだろう”
少年フレッグは後悔していた。
フレッグは女の子2人と男の子3人の計5人で、工場跡の空き地の古いガスタンクの前にいた。
彼らはガスタンクめがけて煉瓦を投げて遊んでいたのだが、ふいに女の子の1人が大声で言った。
「煉瓦のとどくところまでは登れないでしょう」
この一言がすべての始まりだった。
「できるもんか。背の高さぐらいしか登れないさ」
「なんのてっぺんにだって登れらあ」
「なら、あのガスタンクのてっぺんまで登ってごらんなさいよ」
「へっちゃらさ」
そして少女がとどめを刺した。
「さあ、登んなさいよ。ほら、このあたしのハンカチ、これをあのてっぺんにしばってきてよ。あたしの旗をひるがえらせてよ」
てっぺんまではビル5〜6階分ほどの高さがあった。
“両の掌にべとべと汗の玉が吹きだす”
“一段一段のぼるにつれて、だんだんからだが重くなる”
“まるで金縛りにあったように、両手が鉄の支柱にしがみついて、どうしようもない”
到底着きそうにないてっぺんのゴール…。
それまで下から野次や叫び声を送っていた子供たちは、新しい楽しみを見つけたのか、フレッグへの関心をなくし、散り散りバラバラになっていた。
あまりにも自分が可哀想すぎる。
フレッグは恐怖心を払いのけ、勇気をもって一段一段登っていくのだが…。
所収本の作品解説にも書いていたが、どこかカフカ的な側面を残しながら、少年フレッグの心理が巧みに描かれている。結末もシュールで良かった。
(前川祐一訳/加納秀夫編・学生社『イギリス短篇名作集』所収)
(2006.9.4/菅井ジエラ)
トップヘ
All Rights Reserved Copyright (C) 2004-2009,MUSEION.