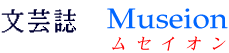
大倉てる子
「紅い外套」
タイピストの濱川松子の頭の中は、あることでいっぱいだった。“お金をどうやって工面すればよいか”
お正月まで、あと2週間しかない。なのに、まだ何の支度もできていないのだ。彼女はいつもその日暮らしのような生活で、月末近くになると一文なしになってしまうこともある。加えて、今年は7つになるひとり娘の三重子が夏の初めに赤痢をやって、その時の医者の払いがそのままになっていた。三重子の外套がもう小さくなってしまっているので、この正月は昨日松坂屋で見た紅い外套を買ってやりたいと思っているが、それもできそうにない。松子は思案にくれていた。
考え事をしていたせいか、仕事が思うように捗らず、気が付くと社でひとりだけになっていた松子。やはり月給の前借りをしないといけないかもしれない。だがそんなことをすると、みんなの前で意地の悪い会計に何を言われるかわからない。彼女は情けなく思いながら、タイプし終わった紙をもって社長室へ行った。
デスクに紙を置いた彼女は、何気なしに部屋にある金庫に目をやった。この中にはたくさんの札束が入っている。彼女にとっては大金だが、社長には一日の小遣いにもならない額のお金。松子は磁石に吸い付けられるように、ふらふらと金庫の前に行った。金庫は冷たく、黒く光っている。金庫の番号は社長と会計、それに松子の3人しか知らなかった。松子はそこで熱病に冒されたようにぼうっとしながら金庫に手をかけた。
“金が欲しい”
そして、開けようとした時…。
「やっと気が付いたね」
松子の後ろに社長がいた。
…。
はじめて知った社長の秘密。掌編ながら、なかなか良かった。
(春日書房『笑ふ花束』所収)
※大倉てる子の“てる”は、火へんに華。
(2006.7.16/菅井ジエラ)
トップヘ
All Rights Reserved Copyright (C) 2004-2013,MUSEION.