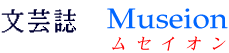|
|
明治文学を読む
●明治文学について
今日、文学は私たちの日常生活において身近な存在になっているが、その昔、文学を一般市民にも普及すべく文芸運動を繰り広げたのが、明治時代に生きた作家たちだった。
明治時代のほとんどの作品が旧かなづかいで書かれているため、文字離れが進んでいる私たちにとっては、読むのがどうしても億劫になりがちだが、読んでみると今日の作品にはない面白さがある。
ここでは「明治文学=教科書に載っている作品」というイメージを払拭し、肩の力を抜いて紹介していきたい。
|
|
|
【明治文学作品】
※緑色で記した作品は順次レビューアップ予定。
黒色で記したものはその年に発表されたその他の作品、著名な作品。
※作品名や引用部分の旧字・旧仮名づかいは、一部改めて記しています。
※リストにあるeBOOKリンクから作品を読むことができます。
明治元年(1868年)
「立憲政体略」(加藤弘之) eBOOK
「薄緑娘白波」(仮名垣魯文)
「報讐殿下茶屋聚」(鈍亭魯文=仮名垣魯文) eBOOK(初篇) eBOOK(二篇)
「窮理図解」(福沢諭吉) eBOOK
明治2年(1869年)
「鉛筆紀聞」(栗本鋤雲) eBOOK
「暁窓追録」(栗本鋤雲) eBOOK
「世界国尽」(福沢諭吉) eBOOK
明治3年(1870年)
「海人の刈藻」(大田垣蓮月=蓮月尼) eBOOK
「真政大意」(加藤弘之) eBOOK(上) eBOOK(下)
「万国航海 西洋道中膝栗毛」(仮名垣魯文) eBOOK
「西国立志編」(中村正直=敬宇訳/スマイルズ著) eBOOK
明治4年(1871年)
「西洋夜話」(寧静学人=石川寧静訳/ピーター・パーレー『万国史』)
eBOOK(初集) eBOOK(二集) eBOOK(三集) eBOOK(四集) eBOOK(五集)
「牛店雑談 安愚楽鍋」(仮名垣魯文) eBOOK(初編) eBOOK(2編上下) eBOOK(3編上下)
「松飾徳若譚」(仮名垣魯文)
「菊模様皿山奇談」(三遊亭円朝) eBOOK(上) eBOOK(下) eBOOK2
明治5年(1872年)
「河童相伝胡瓜遣」(仮名垣魯文) eBOOK(初編上) eBOOK(初編下)
「自由之理」(中村正直訳/ミル著) eBOOK
「学問のすすめ」(福沢諭吉) eBOOK
「かたわ娘」(福沢諭吉) eBOOK eBOOK2
「通俗 伊蘇普物語」(Thomas James英訳・無尽蔵書斎主人=渡部温和訳/イソップ物語237話)
eBOOK(巻之一) eBOOK(巻之二) eBOOK(巻之三)
eBOOK(巻之四) eBOOK(巻之五) eBOOK(巻之六)
明治6年(1873年)
「国体新論」(加藤弘之) eBOOK
「横文字百人一首」(黒川真頼撰) eBOOK
「近世紀聞」(染崎延房編) eBOOK
「復古夢物語」(松村春輔) eBOOK(初編上/第1回・第2回) eBOOK(初編下/第3回・第4回)
eBOOK(二編上/第5回・第6回) eBOOK(二編下/第7回・第8回)
eBOOK(三編上/第9回・第10回) eBOOK(三編中/第11回・第12回) eBOOK(三編下/第13回・第14回)
eBOOK(四編上/第15回・第16回) eBOOK(四編下/第17回・第18回)
eBOOK(筑波ノ部五編上/第19回・第20回)
eBOOK(筑波ノ部五編下/第21回・第22回)
eBOOK(六編上/第23回・第24回)
eBOOK(六編下/第25回・第26回)
eBOOK(七編上/第27回・第28回)
eBOOK(七編下/第29回・第30回)
eBOOK(八編上/第31回・第32回)
eBOOK(八編下/第33回・第34回)
「大鈍託新文鬼談」(万亭応賀)
「新制兎美断語」(万亭応賀) eBOOK
「和談三才図笑」(万亭応賀) eBOOK
明治7年(1874年)
「開化進歩 後世夢物語」(上條信次訳/ジオスコリデス『西暦2065年』) eBOOK
「阿玉ケ池櫛月形」(山々亭有人=条野採菊)
「義烈回天百首」(染崎延房編) eBOOK
「耶蘇一代弁妄記」(田島象二) eBOOK(初編上) eBOOK(初編下) eBOOK(二編上) eBOOK(二編下)
「柳橋新誌」(成島柳北) eBOOK(初編) eBOOK(二編)
「京猫一斑」(成島柳北)
「知説」(西周) eBOOK
「致知啓蒙」(西周) eBOOK(第一巻) eBOOK(第二巻)
「百一新論」(西周) eBOOK(巻之上) eBOOK(巻之下)
「東京新繁盛記」(服部誠一=服部撫松) eBOOK
「分限正札 智恵秤」(万亭応賀) eBOOK
明治8年(1875年)
「怪化百物語」(高畠藍泉=転々堂主人) eBOOK(上) eBOOK(下)
「開巻驚奇 暴夜物語」(永峰秀樹訳/アラビアンナイトの抄訳) eBOOK(巻之一) eBOOK(巻之二)
「美妙学説」(西周)
「文明論之概略」(福沢諭吉) eBOOK
明治9年(1876年)
「埋木廼花」(高崎正風編)
「一大奇書書林之庫」(田島象二)
「金之助之話」(前田夏繁=前田香雪)
「開明小説春雨文庫」(松村春輔) eBOOK(二編上)
明治10年(1877年)
「新説 八十日間世界一周」(川島忠之助訳/ヴェルヌ著) eBOOK
「鳥追お松の伝(改題/鳥追阿松海上新話)」(久保田彦作) eBOOK
「日本開化小史」(田口卯吉) eBOOK
明治11年(1878年)
「欧州奇事 花柳春話」(織田純一郎=丹羽純一郎訳/リットン著)
eBOOK(第一篇/第一章~第十六章) eBOOK(第二篇/第十七章~第三十二章)
eBOOK(第三篇/第三十三章~第四十九章) eBOOK(第四篇/第五十章~第六十六章)
「新未来記」(近藤真琴訳/ジオスコリデス『西暦2065年』) eBOOK(上) eBOOK(下)
「塩原多助一代記」(三遊亭円朝) eBOOK
「西洋品行論」(中村正直=敬宇訳/スマイルズ著) eBOOK
明治12年(1879年)
「水錦隅田曙」(伊東専三) eBOOK(初編上) eBOOK(初編中) eBOOK(初編下)
eBOOK(二編上) eBOOK(二編中) eBOOK(二編下)
eBOOK(三編上) eBOOK(三編中) eBOOK(三編下)
「九十七時二十分間月世界旅行」(井上勤訳/ヴェルヌ著) eBOOK
「民権田舎歌」(植木枝盛) eBOOK
「民権自由論」(植木枝盛) eBOOK
「其名も高橋毒婦の小伝 東京奇聞」(岡本起泉)
「島田一郎梅雨日記」(岡本起泉) eBOOK
「欧洲奇話 寄想春史」(織田純一郎訳/リットン著) eBOOK(初篇) 第二篇 eBOOK(第三篇)
「高橋阿伝夜刃譚」(仮名垣魯文) eBOOK
「巷説児手柏」(高畠藍泉)
「民情一新」(福沢諭吉) eBOOK
「欧州小説 哲烈禍福譚」(宮島春松訳・仮名垣魯文序/フェヌロン著) eBOOK(巻之一) eBOOK(巻之二)
eBOOK(巻之三) eBOOK(巻之四) eBOOK(巻之五) eBOOK(巻之六) eBOOK(巻之七) eBOOK(巻之八)
「西洋滑稽 三笑人」(山田保抄訳/原著不明) eBOOK eBOOK(二版)
明治13年(1880年)
「開巻驚奇 龍動(ロンドン)鬼談」(井上勤訳/リットン著)
「民権数へ歌」(植木枝盛)
「鵝■□兒回島記(ガリバルスしまめぐり)(■は王へんに黎、□は白へんに番)」(片山平三郎訳/スウィフト『ガリバー旅行記』) eBOOK
「蓆旗群馬嘶(むしろばたぐんまのいななき)」(彩霞園柳香編)
eBOOK(第一編上) eBOOK(第一編中) eBOOK(第一編下)
eBOOK(第二編上) eBOOK(第二編中) eBOOK(第二編下)
「南の海血潮の曙」(坂崎紫瀾)
「冠松真土夜暴動」(武田交来編)
eBOOK(前編上) eBOOK(前編中) eBOOK(前編下)
eBOOK(後編上) eBOOK(後編中) eBOOK(後編下)
「春風情話」(橘顕三=坪内逍遥意訳/スコット著) eBOOK(第一編)
「民権演義 情海波瀾」(戸田欽堂) eBOOK(第一編)
「落花清譚 春風日記」(松村春輔=桜雨園)
eBOOK(初編之一) eBOOK(初編之二) eBOOK(二編巻之上) eBOOK(二編巻之下)
eBOOK(三編之上) eBOOK(三編之下) eBOOK(第四編上) eBOOK(第四編下)
eBOOK(第五編上) eBOOK(第五編下) eBOOK(六編之上) eBOOK(六編之下)
明治14年(1881年)
「怪化娘出世指南」(池田喜多治=箆棒痴人) eBOOK
「川上行義復讐新話」(岡本起泉)
「嶋鵆月白波」(河竹黙阿弥) eBOOK
「天衣紛上野初花」(河竹黙阿弥) eBOOK
「怪化狂詩撰」(島田主善=夢春) eBOOK(上) eBOOK(下)
「西国烈女伝(改題/婦女立志 欧州美談)」(田島象二編) eBOOK eBOOK2
「航西日乗」(成島柳北)
「東京粋書」(野崎左文=憑空逸史) eBOOK(初編)
「恋仇花盛街夕暮」(番亭楽山) eBOOK(初編上) eBOOK(初編中) eBOOK(初編下)
eBOOK(二編上) eBOOK(二編中) eBOOK(二編下) eBOOK(三編上) eBOOK(三編中) eBOOK(三編下)
「小学唱歌集」(文部省編) eBOOK(初編) eBOOK(第二編) eBOOK(第三編)
「仏国情話 五九節操史」(松岡亀雄訳/歴山戎馬斯=デュマ著) eBOOK(第一篇) eBOOK(第二篇) eBOOK(第三篇)
「忘貝」(村山松根) eBOOK(上) eBOOK(下)
明治15年(1882年)
「良政府談」(井上勤訳/トマス・モア『ユートピア』) eBOOK
「新体詩抄」(井上哲次郎・外山正一・矢田部良吉) eBOOK(初編)
「春霞筑波曙」(宇田川文海)
「雁信壺の碑」(宇田川文海)
「欧洲情譜 群芳綺話」(大久保勘三郎訳/ボッカッチョ『デカメロン』)
「地獄極楽一周記 : 文明開化」(大久保夢遊) eBOOK
「虚無党退治奇談」(川島忠之助訳/ポール・ヴェルニエ著)
「英国情史 蝶舞奇縁」(顧柳散人=桑野鋭訳/原著者不明『Albinia; Or, the Young Mother』)
eBOOK(初篇) 二篇 三篇 四篇
「東洋自由の曙」(坂崎紫瀾)
「仏国革命起源 西洋血潮小暴風」(百華園主人=桜田百衛訳/デュマ著)
「魯国奇聞 烈女の疑獄」(杣田策太郎抄訳/魯国の烈女ヴェラサシュリッチの糺問の記) eBOOK
「岡山紀聞筆の命毛」(高畠藍泉)
「民約訳解」(中江兆民訳/ルソー著)
「千万無量 星世界旅行 一名 世界蔵」(貫名駿一) eBOOK
「仏蘭西革命記 自由乃凱歌」(宮崎夢柳翻案/デュマ著) eBOOK(第二編)
「ハムレット」(矢田部良吉訳/シェイクスピア著)
「哲爾自由譚 一名 自由之魁」(松湖漁史=山田郁治訳/視而列爾=シラー『ヴィルヘルム・テル』) eBOOK(前編)
明治16年(1883年)
「経世指針 鉄烈奇談」(伊澤信三郎訳/フェヌロン『テレマックの冒険』) eBOOK(巻之一 第一篇~巻之五 第五篇)
「開明奇談写真廼仇討」(伊東専三) eBOOK
「花春時相政」(伊東専三) eBOOK
「六万英里 海底紀行」(井上勤訳/ヴェルヌ著) eBOOK
「亜非利加内地三十五日間空中旅行」(井上勤訳/ヴェルヌ著) eBOOK(巻之1) eBOOK(巻之2)
eBOOK(巻之3) eBOOK(巻之4) eBOOK(巻之5) eBOOK(巻之6) eBOOK(巻之7)
「西洋珍説 人肉質入裁判」(井上勤訳/西基斯比耶=シェイクスピア『ヴェニスの商人』) eBOOK
「全世界一大奇書」(井上勤訳/アラビアンナイト) eBOOK
「絶世奇談 魯敏孫漂流記」(井上勤訳/デフォー『ロビンソン・クルーソー』) eBOOK
「橋供養梵字文覚」(竹柴金作=三世河竹新七) eBOOK(上)
「勤王為経民権為緯新編大和錦」(小室案外堂)
「法燈将滅高野暁」(小室案外堂)
「天下無双人傑海南第一伝奇 汗血千里駒」(坂崎鳴々道人=紫瀾) eBOOK(初編)
(「汗血千里駒」(坂崎紫瀾著・雑賀柳香補綴)) eBOOK
「仏国革命修羅の衢」(坂崎紫瀾)
「阿国民造 自由廼錦袍」(桜田百衛) eBOOK
「露国奇聞 花心蝶思録」(高須治助訳/プーシキン『大尉の娘』) eBOOK
「新奇妙談 閻魔大王判決録」(高瀬紫峰) eBOOK
「維氏美学」(中江兆民訳/ウージェヌ・ヴェロン著) eBOOK(上) eBOOK(下)
「天賦人権論」(馬場辰猪) eBOOK
「浅尾岩切真実競」(松亭鶴仙) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「経国美談」(矢野龍渓) eBOOK
「小夜千鳥浪の音信」(三品藺渓=柳条亭華彦) eBOOK(前) eBOOK(後)
明治17年(1884年)
「独逸奇書 狐の裁判」(井上勤訳/ゲーテ著) eBOOK
「白露革命外伝 自由廼征矢」(井上勤訳/ヴェルヌ『マルティン・パス』) eBOOK
「五大洲中 海底旅行」(大平三次訳/ヴェルヌ著) eBOOK(上編) eBOOK(下編)
「惨風悲雨 世路日記」(菊亭香水) eBOOK
「回天偉績 仏国美談」(粟屋関一訳/ゼーネット・タッキー著)
「興亜綺談 夢恋々」(小室案外堂) eBOOK
「自由艶舌女文章」(小室案外堂) eBOOK
「南山皇旗の魁」(坂崎紫瀾)
「怪談牡丹燈籠」(三遊亭円朝) eBOOK
「黄金の花籠」(須藤南翠)
「政党余談 春鶯囀」(関直彦訳/ディズレイリ『コニングスビー』) eBOOK(第一編) eBOOK(第二編)
eBOOK(第三編 初音の巻) eBOOK(第四編 百囀の巻)
「新体 漢字破」(外山正一) eBOOK
「羅馬字会を起すの趣意」(外山正一)
「該撒奇談 自由太刀余波鋭鋒」(坪内雄蔵=坪内逍遥訳/シェイクスピア『ジュリアス・シーザー』) eBOOK
「泰西活劇 春窓綺話」(服部誠一=服部撫松編訳/スコット『湖上の美人』) eBOOK(上篇) eBOOK(下篇)
「第二世夢想兵衛胡蝶物語」(服部撫松)
「文明東漸史」(藤田茂吉) eBOOK
「一滴千金 憂世の涕涙」(宮崎夢柳訳/エドワード・キング著) eBOOK(巻之一) 巻之二 巻之三
「虚無党実伝記 鬼啾啾」(宮崎夢柳訳/ステプニャック著)
明治18年(1885年)
「那翁外伝 閨秀美談」(秋庭濱太郎訳/亜勃的=アボット著) eBOOK
「破邪新論」(井上甫水=井上円了) eBOOK
「雲間月」(宇田川文海) eBOOK
「江嶋土産滑稽貝屏風」(尾崎紅葉)
「趣向ハ沙士比阿の肉一片文章は柳亭種彦の正本製 何桜彼桜銭世中 花莚七枚」
(雨の家狸遊編・宇田川文海閲/シェイクスピア『ヴェニスの商人』) eBOOK
「諷世嘲俗 繋思談」(藤田茂吉・尾崎庸夫合訳/リットン著) eBOOK(初編) eBOOK(中編)
「英国名士 回天綺談」(加藤政之助編訳) eBOOK
「余波の水茎」(乞食井月)
「西洋人情話 英国孝子ジョージスミス之伝」(三遊亭円朝演述) eBOOK(第一編)
eBOOK(第二編) eBOOK(第三編) eBOOK(第四編) eBOOK(第五編)
eBOOK(第六編) eBOOK(第七編) eBOOK(第八編)
「春色日本魂」(楊外堂主人=須藤南翠) eBOOK
「新編黄昏日記」(醒々居士=小宮山天香 稿・天香逸史=小宮山天香 閲/歴山徳戎馬=デュマ・フィス『椿姫』) eBOOK
「黒白染分■(こくびゃくそめわけたづな)(■は革へんに疆のつくり)」(柳亭種彦=高畠藍泉) eBOOK(上) eBOOK(下)
「開巻悲憤 慨世士伝」(坪内逍遙訳/リットン著)
「小説神髄」(坪内逍遙) eBOOK
「一読三歎 当世書生気質」(坪内逍遙) eBOOK
「佳人之奇遇」(東海散士)
「情態奇話 人七癖」(二愛亭花実・淡々亭如水合訳/ウージェーヌ・シュー著)
eBOOK(吝嗇編 第一回・第三回~第九回) eBOOK(吝嗇編 第二回)
「擬紫西洋天一坊」(早川居士智静=早川熊吉編) eBOOK
「日本婦人論」(福沢諭吉) eBOOK
「欧洲忠臣蔵」(愛華仙史=三木貞一訳述) eBOOK
「竪琴草紙」(山田美妙)
「十二の石塚」(湯浅半月) eBOOK
「壽其徳奇談」(横山半呂久訳/スコット『Tales of a Grandfather』)
明治19年(1886年)
「当世商人気質」(饗庭篁村) eBOOK
「人の噂」(饗庭篁村) eBOOK
「政治小説 梅蕾余薫」(牛山鶴堂訳/権男爵蘇骨=スコット『アイヴァンホー』)
eBOOK(前篇) eBOOK(後篇)
「婦人地球週遊記」(内田彌八訳/ブラッセー著) eBOOK(第一巻)
「名将佳人 遠征奇縁 一名 西洋水滸伝」(小野次郎編訳/原著者不明) eBOOK
「修羅浮世 鍛鉄場主 一名 生活の戦場」(聯画閑人=加藤瓢乎訳/オネー著) eBOOK
「沙吉比亜戯曲 羅馬盛衰鑑」(鶯林学人=河島鶯林=河島敬蔵・天香逸史=小宮山天香戯訳/シェイクスピア『ジュリアス・シーザー』) eBOOK
「露妙樹利戯曲 春情浮世之夢」(河島敬蔵訳/沙士比阿=シェイクスピア『ロミオとジュリエット』) eBOOK
「和蘭美政録 楊牙児(ヨンゲル)奇談」(神田孝平訳・成島柳北編/クリストマイエル「ヨンケル・ファン・ロデレイケ」) eBOOK
「ボッカース翁十日物語 想夫恋」(臥牛樓=佐野尚訳/ボッカッチョ著) eBOOK
「英国小説 草葉の露」(ブラック口述・市東謙吉筆記/ブレドン(Braddon)『Flower and Weed』) eBOOK
「セキスピヤ物語」(品田太吉訳/チャールズ・ラム『シェイクスピア物語』) eBOOK
「政治小説 雪中梅」(末広重恭=末広鉄腸) eBOOK
「二十三年未来記」(末広重恭=末広鉄腸) eBOOK
「演劇改良意見」(末松謙澄) eBOOK
「雨窓漫筆 緑蓑談」(須藤南翠) eBOOK
「一頻一笑新粧乃佳人」(須藤南翠)
「シェキスピーヤ筋書 一名 西洋歌舞伎種本」(竹内余所次郎訳/チャールズ・ラム『シェイクスピア物語(リア王)』) eBOOK
「内地雑居未来の夢」(春のや主人=坪内逍遥) eBOOK
「泰西女丈夫伝 朗蘭婦人伝(改題/淑女亀鑑 交際の女王)」(春廼屋朧=坪内逍遥訳) eBOOK
「将来之日本」(徳富蘇峰) eBOOK
「演劇改良論私考」(外山正一) eBOOK
「維廉得自由一箭(ウヒルヘルムテルじいうのひとや)」(中川霞城訳/シラー『ヴィルヘルム・テル』)
「世界進歩 第二十世紀」(服部撫松訳/アルベール・ロビダ『20世紀』)
eBOOK(第一編) eBOOK(第二編) eBOOK(第三編)
「二十三年国会未来記」(服部誠一=服部撫松) eBOOK(第一編) eBOOK(第二編)
「男女交際論」(福沢諭吉) eBOOK
「万里絶域 北極旅行」(福田直彦訳/ヴェルヌ著) eBOOK
「小説総論」(二葉亭四迷) eBOOK
「一読千歎 欧洲書生気質」(寸木田人=村田豊作訳/Wilhelm Schroeder著) eBOOK(第一号)
「泣花怨柳 北欧血戦余塵」(森體抄訳/鄧都意=トルストイ『戦争と平和』) eBOOK(第一巻)
「周遊雑記」(矢野文雄=矢野龍渓) eBOOK(上)
「嘲戒小説天狗」(山田美妙)
「貞操 英国美譚」(訳者不明・鎗田主人=鎗田かね編/著者不明) eBOOK
「三英双美 政海の情波」(渡邊治訳/俾君斯裨徳伯=ビーコンズフィールド伯爵ディズレイリ『エンディミオン』)
eBOOK(第一巻) eBOOK(第二巻) eBOOK(第三巻) eBOOK(第四巻)
明治20年(1887年)
「黒猫」(饗庭篁村訳/ポー著)
「ルーモルグの人殺し」(竹の舎主人=饗庭篁村訳/ポー著)
「サクソン王の名残 ハロールド物語」(依緑軒=磯野徳三郎訳/リットン『Harold, the Last of the Saxon Kings』) eBOOK
「政治小説 妻の嘆」(井上勤訳/維児機胡林斯=ウィルキー・コリンズ『夫と妻』) eBOOK
「学術妙用 造物者驚愕試験」(井上勤訳/ヴェルヌ「オクス博士の幻想」) eBOOK
「欧州奇説 恋情花之嵐(れんじょうはなのあらし)」(香夢楼主人=岩本吾一訳/ル・サージュ著) eBOOK
「日本新世界」(牛山良介=牛山鶴堂) eBOOK
「社会小説 日本之未来」(牛山良介=牛山鶴堂) eBOOK(上編) eBOOK(下編)
「雙鶯春話」(牛山良助訳/ビーコンズフィールド伯爵ベンジャミン・ディズレイリ『ヘンリエッタ・テンプル(Henrietta Temple)』)
「人情小説 花情粋話」(大石高徳意訳/Vittorio Bersezio『Nouvelles Piemontaises』) eBOOK
「改良小説 奇遇魯国美談」(大石高徳訳/ドンベイ父子『ボン・フレール』) eBOOK
「政教小説 蒙里西物語」(大石高徳編訳/Z・カロー女史『Maurice ou le Travail』) eBOOK
「東京未来繁昌記」(夢遊居土=大久保常吉) eBOOK
「娘博士」(尾崎紅葉)
「世界文明 宇宙之舵蔓(せかいぶんめいうちゅうのかじづる)」(勝岡信三郎編訳/原著者不明) eBOOK eBOOK2
「社会進化 世界未来記」(蔭山広忠訳/アルベール・ロビダ『20世紀』) eBOOK eBOOK2
「筑紫潟松千代咲」(川尻宝岑)
「哀別奇遇 誠之鏡」(春煙小史=赤司新三郎訳/塞格斯比亜=シェイクスピア『ペリクリーズ』) eBOOK
「仇結奇之赤縄 西洋娘節用」(春煙小史=木下新三郎訳/シェイクスピア『ロミオとジュリエット』) eBOOK
「中国怪談集」(小泉八雲)
「慨世史談 断蓬奇縁」(小宮山天香訳/チヤートリアン著) eBOOK
「冒険企業聯島大王」(小宮山天香)
「欧洲新話 谷間之鶯」(齋藤良恭訳/セルバンテス『ドン・キホーテ』より) eBOOK
「浮世人情 守銭奴の肚」(嵯峨の屋おむろ=矢崎嵯峨の屋) eBOOK
「ひとよぎり」(嵯峨の屋おむろ=矢崎嵯峨の屋) eBOOK
「欧洲小説 黄薔薇」(三遊亭円朝口述/デュマ・フィス著?) eBOOK
「南洋時事」(志賀重昂) eBOOK
「折枝の梅が香(改題/第一の佳人)」(採菊散人=条野採菊訳/アルノー『メゼリー』) eBOOK eBOOK2
「小説 雨中花」(末広鉄腸=末広重恭・二宮孤松同訳/原著者不明) eBOOK
「政治小説花間鶯」(末広鉄腸) eBOOK
「西洋古事 神仙叢話」(桐南居士=菅了法訳/グリム童話より) eBOOK
「春暁攪眠 痴人の夢」(須藤南翠) eBOOK
「開巻驚奇 西洋復讐奇譚」(橘邨居士=関直彦訳/デュマ・ペール『モンテ・クリスト伯』) eBOOK(前編)
「梨園の曙 一名 西洋演劇脚本」(高橋義雄編訳/Henry A. Jones, George Soane, George Macfarren, T. A. Palmer著) eBOOK
「非自由結婚談 恋之夜暴風」(東海道人補編・咄々怪人校閲) eBOOK
「新日本之青年」(徳富猪一郎=徳富蘇峰) eBOOK
「三酔人経綸問答」(南海仙漁=中江兆民) eBOOK
「一読一驚 世界一大奇聞」(諸大家先生訳述・中沢順三編) eBOOK
「善悪の岐」(中島湘烟) eBOOK
「欧洲情史 美人の罠」(中村柳塢訳/セルバンテス『ドン・キホーテ』より) eBOOK
「法理小説 百難錦」(柳下亭美登利=西岡鷺南翻案) eBOOK
「屑屋の籠」(西村天囚) eBOOK
「五日紀変 英雄之肝胆」(野田栄城=野田藤吉郎訳/ユゴー著) eBOOK(上)
「文学小説 連理談」(服部誠一=服部撫松訳/リットン『ユージン・アラム』) eBOOK
「代議政談 月雪花」(久松義典) eBOOK(前編)
「南溟偉蹟」(久松義典) eBOOK(前編)
「女子参政 蜃中楼」(広津柳浪) eBOOK
「済民偉業録」(藤田茂吉) eBOOK(前編)
「浮雲」(二葉亭四迷) eBOOK
「新案奇想英和小説 新世帯 一名 恋娘」(芳丘居士=本多金十郎抄訳/ウイリアム・ギルバート『The Wizard of the Mountain』) eBOOK
「鮮血日本刀」(本多孫四郎訳/フォーセット『クリスマス前夜の犯罪』) eBOOK
「波斯新説 烈女之名誉(れつじょのほまれ)」(村上眞助抜萃/アラビアンナイト) eBOOK
「才子妙案 天外奇談」(村田一嘯評語・東条種家編述/The Hotel's Odd Story) eBOOK
「欧洲小説 西洋梅暦 一名 恋情月の叢雲」(森知齋・福田直彦合訳/グールドン・ジェヌイヤック著) eBOOK
「瞽使者(盲目使者)」(羊角山人=森田思軒訳/ヴェルヌ著) eBOOK(上編) eBOOK(下編)
「仏・曼二学士の譚(改題/鉄世界)」(森田文蔵=森田思軒訳/ヴェルヌ『インド王妃の遺産』) eBOOK
「他邦侵略 露人気質」(米の舎半痴=八木半治訳/エルマック伝) eBOOK
「武蔵野」(山田美妙) eBOOK
「侠美人」(依田百川=依田学海) eBOOK(第一篇) eBOOK(第二篇)
「吉野拾遺名家誉」(依田学海) eBOOK(上) eBOOK(下)
「脚本ハ仏国 世界ハ日本 当世二人女婿」(依田百川=依田学海戯編・秋濤外史=長田秋濤原訳/シェイクスピア『リア王』) eBOOK(巻上) eBOOK(巻下)
明治21年(1888年)
「一喜一憂 捨小舟」(石橋忍月) eBOOK
「新体詩歌自由詞林」(植木枝盛)
「美人の俤」(大橋乙羽)
「裁判小説 秋暮嘆」(岡野碩(訳?)) eBOOK
「浮世の巷」(岡野碩翻案/ウージェーヌ・シュー『パリの秘密』) eBOOK(前編)
「保安條例後日之夢」(半渓老漁=岡本半渓=岡本純) eBOOK
「新開場梅田神垣」(川尻宝岑)
「籠釣瓶花街酔醒」(竹柴金作=三世河竹新七) eBOOK
「裁判小説 人耶鬼耶」(黒岩涙香訳/エミール・ガボリオ著) eBOOK
「法廷の美人」(黒岩涙香訳/ヒュー・コンウェイ著)
「御垣の下草」(税所敦子) eBOOK(上) eBOOK(下)
「無味気」(嵯峨の屋おむろ) eBOOK
「滑稽狂言 双児の邂逅」(相良常雄訳/プラウトゥス『メナエクムス兄弟』) eBOOK
「東洋之佳人」(柴四郎=東海散士) eBOOK
「政治小説 小人国発見録」(島尾岩太郎訳/スウィフト『ガリヴァー旅行記』) eBOOK
「硝烟劔鋩 殺人犯」(須藤南翠) eBOOK
「妖怪船」(杏堂散史=高橋礼五郎訳/ヴィルヘルム・ハウフ「隊商」一章) eBOOK
「泰西奇譚 旅路之空」(柏城逸士=田口祐吉訳/巴烏弗=ハウフ「メルヘン」) eBOOK
「摘陰発微 奇獄」(千原伊之吉訳/George McWatters『Detectives of Europe & America』) eBOOK
「贋貨つかひ(贋もの/贋貨百万円)」(春のやおぼろ=坪内逍遥訳/アンナ・キャサリン・グリーン『XYZ』)
「泰西奇談 嵐の巻」(叢菊野史=仁田桂次郎訳/シェイクスピア『テンペスト』) eBOOK
「泰西奇談 智孟物語」(叢菊野史=仁田桂次郎訳/シェイクスピア『アテネのタイモン』) eBOOK
「泰西奇談 女房持虎の巻」(叢菊野史=仁田桂次郎訳/シェイクスピア『じゃじゃ馬ならし』) eBOOK
「闇中政治家」(原抱一庵)
「もしや草紙」(福地桜痴) eBOOK
「あひびき」(二葉亭四迷訳/ツルゲーネフ著) eBOOK
「めぐりあひ」(二葉亭四迷訳/ツルゲーネフ著)
「散浮花」(延春亭主人=丸岡九華)
「千代之礎」(三浦徹訳/O. F.ウォルトン『Saved at Sea. A Lighthouse Story』) eBOOK
「藪の鶯」(三宅花圃) eBOOK
「嵯峨の尼物語」(宮崎三昧) eBOOK
「芒の一と叢」(宮崎夢柳) eBOOK
「大東号航海日記」(森田思軒訳/ヴェルヌ著)
「炭坑秘事」(紅勺園主人=森田思軒訳/ヴェルヌ著)
「夏木立」(山田美妙)
「花車」(山田美妙)
「鏡花水月」(渡邉治訳/シェイクスピア『間違いの喜劇』) eBOOK
「みなれざを」(わだのとろみ=和田万吉訳/沙翁=シェイクスピア『終わりよければ全てよし』) eBOOK
明治22年(1889年)
「良夜」(饗庭篁村) eBOOK
「改良小説著作法」(高山處士=朝戸善友) eBOOK
「百美人」(淡島寒月)
「旅画師」(江見水蔭)
「二人比丘尼色懺悔」(尾崎紅葉) eBOOK
「Yes and No」(尾崎紅葉)
「恋」(奥村柾兮=大東楼愚人) eBOOK
「椿の花把」(加藤紫芳訳/亜歴山戌馬男=デュマ・フィス『椿姫』 eBOOK
「楚囚之詩」(北村透谷) eBOOK
「勇み肌」(木村曙)
「婦女の鑑」(木村曙)
「無惨」(黒岩涙香) eBOOK
「あやしやな」(幸田露伴) eBOOK
「奇男児」(幸田露伴) eBOOK
「露団々」(幸田露伴) eBOOK
「風流仏」(幸田露伴) eBOOK
「小説八宗」(正直正太夫=斎藤緑雨) eBOOK
「悪魔」(堺利彦)
「くされ玉子」(嵯峨の屋おむろ)
「野末の菊」(嵯峨の屋おむろ)
「初恋」(嵯峨の屋おむろ) eBOOK
「流転」(嵯峨の屋おむろ)
「とりかへばや」(条野採菊)
「三都の花」(武田仰天子) eBOOK
「政治小説 条約改正」(塚原渋柿園) eBOOK(初編)
「細君」(坪内逍遙) eBOOK
「埃及近世史」(柴四郎=東海散士) eBOOK
「山間の名花」(中島湘烟)
「海王丸」(半井桃水) eBOOK
「くされ縁」(半井桃水)
「残菊」(広津柳浪)
「女子参政 蜃中樓」(広津柳浪) eBOOK
「水と石」(前田香雪)
「夜と朝」(益田克徳訳/リットン著) eBOOK
「折薔薇」(三木竹二・森鴎外共訳/レッシング著) eBOOK
「音調高洋筝一曲(改題/調高矣洋絃一曲)」(三木竹二・森鴎外共訳/カルデロン著) eBOOK
「花盗人」(柳塢情史=右田寅彦) eBOOK
「盲目の美人」(柳塢散史=右田寅彦) eBOOK
「蓮池水禽」(南新二)
「於母影」(森鴎外・落合直文・井上通泰・小金井きみ子(小金井喜美子)・市村さん[鑽の偏が王偏]次郎共訳)
「探偵ユーベル」(森田思軒訳/ユーゴー著) eBOOK
「いちご姫」(山田美妙) eBOOK
「胡蝶」(山田美妙) eBOOK eBOOK2
明治23年(1890年)
「露小袖」(大橋乙羽)
「伽羅枕」(尾崎紅葉) eBOOK
「新色懺悔」(尾崎紅葉) eBOOK
「西印度諸島の二年間」(小泉八雲)
「縁外縁(改題/対髑髏)」(幸田露伴) eBOOK
「ひげ男」(幸田露伴) eBOOK
「一口剣」(幸田露伴) eBOOK
「廻瀾」(高瀬文淵)
「め組の喧嘩」(竹柴其水)
「水郷の夢」(徳富蘆花)
「日本絵画ノ未来」(外山正一) eBOOK
「九十九の嫗」(中西梅花) eBOOK
「桧木笠」(中村花痩)
「業平竹」(半井桃水) eBOOK
「門出小草」(野口寧斎)
「滑稽小説 二人花婿」(堀成之=烟亭紫山人) eBOOK
「自惚娘」(槇野半酔) eBOOK
「鎌倉武士」(南新二) eBOOK
「帰省」(宮崎湖処子) eBOOK
「桂姫」(宮崎三昧) eBOOK
「小説家」(村井弦斎) eBOOK(上之巻) eBOOK(下之巻)
「舞姫」(森鴎外) eBOOK
「うたかたの記」(森鴎外) eBOOK
「報知異聞浮城物語」(矢野龍渓) eBOOK
「小公子」(巌本嘉志子=若松しづ子(若松賤子)訳/バーネット著) eBOOK
明治24年(1891年)
「こがね丸」(厳谷小波) eBOOK
「二人女房」(尾崎紅葉) eBOOK
「蓬莱曲」(北村透谷) eBOOK
「いさなとり(小説勇魚捕)」(幸田露伴) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「艶魔伝(風流艶魔伝)」(幸田露伴) eBOOK
「五重塔」(幸田露伴) eBOOK
「辻浄瑠璃」(幸田露伴) eBOOK eBOOK2
「寝耳鉄砲」(幸田露伴) eBOOK eBOOK2
「風流悟」(幸田露伴)
「大通世界」(幸堂得知) eBOOK(第1~3号)
「浦島次郎蓬莱噺」(幸堂得知) eBOOK
「酔骨録」(小杉天外) eBOOK
「油地獄」(斎藤緑雨) eBOOK
「かくれんぼ」(斎藤緑雨) eBOOK
「夢現境」(嵯峨の屋おむろ)
「文学及人生」(高山樗牛)
「新日本史」(竹越三叉)
「瓜畑」(古桐軒主人=田山花袋)
「離れ鴦」(中村花痩)
「新体梅花詩集」(中村梅花) eBOOK
「胡砂吹く風」(半井桃水) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「月珠」(省庵居士=原抱一庵訳/コリンズ著)
「演劇脚本 春日局」(福地桜痴) eBOOK
「幕府衰亡論」(福地源一郎=福地桜痴) eBOOK
「江戸桜」(前田曙山)
「真善美日本人」(三宅雪嶺) eBOOK
「空屋」(宮崎湖処子) eBOOK
「吾亡妻」(宮崎三昧)
「小猫」(村井弦斎) eBOOK
「井筒女之助」(ちぬの浦浪六=村上浪六) eBOOK
「三日月」(ちぬの浦浪六=村上浪六) eBOOK
「文づかひ」(森鴎外) eBOOK
「盗賊秘事」(山田美妙) eBOOK
明治25年(1892年)
「三人妻」(尾崎紅葉) eBOOK
「塩原多助一代記」(竹柴金作=三世河竹新七) eBOOK
「怪異談牡丹燈籠」(竹柴金作=三世河竹新七) eBOOK
「鶯宿梅」(菊池幽芳)
「厭世詩家と女性」(北村透谷) eBOOK
「我牢獄」(北村透谷) eBOOK
「浴泉記」(小金井喜美子訳/レールモントフ著)
「当世志士伝」(小杉天外)
「肥えた旦那」(堺利彦)
「没理想の語義を弁ず」(坪内逍遙) eBOOK
「うもれ木」(樋口一葉) eBOOK
「たま襷」(樋口一葉) eBOOK
「闇桜」(樋口一葉) eBOOK
「別れ霜」(樋口一葉) eBOOK
「獺祭書屋俳話」(正岡子規) eBOOK
「小説 みだれ咲」(夢借舎丁々子=三宅花圃) eBOOK
「我観小景」(三宅雄二郎=三宅雪嶺) eBOOK
「白雲」(宮崎湖処子)
「塙団右衛門」(宮崎三昧) eBOOK
「奴の小万」(村上浪六) eBOOK
「即興詩人」(森鴎外訳/アンデルセン著) eBOOK
明治26年(1893年)
「薄皮美人」(浮世舎まゝよ) eBOOK
「黒猫」(内田貢=内田魯庵訳/ポー著) eBOOK
「雪の女王」(内田貢=内田魯庵訳/アンデルセン著) eBOOK
「基督信徒の慰め」(内村鑑三) eBOOK
「隣の女」(尾崎紅葉) eBOOK
「人生に相渉るとは何の謂いぞ」(北村透谷) eBOOK
「内部生命論」(北村透谷) eBOOK
「枕頭山水」(幸田露伴) eBOOK
「風流微塵蔵」(幸田露伴)
「悪太郎」(堺利彦)
「継母根性」(堺枯川=堺利彦) eBOOK
「はだか男」(堺枯川=堺利彦) eBOOK
「痘痕伝七郎 : 一名・花の深山木」(採菊散人=條野伝平=条野採菊翻案/シェイクスピア『オセロー』) eBOOK
「茨木阿滝紛白糸」(土屋南翠=須藤南翠) eBOOK
「滑稽長屋」(痩々亭骨皮道人) eBOOK
「詩篇 若葉」(高瀬文淵) eBOOK
「小詩人」(田山花袋) eBOOK
「マコウレー」(竹越三叉)
「桂川」(戸川残花)
「情死を弔ふ歌」(戸川残花)
「碓氷の紅葉(改題/両毛の秋)」(徳富健次郎=徳富蘆花) eBOOK
「近世欧米歴史之片影」(徳富健次郎=徳富蘆花) eBOOK
「百合の花」(徳富健次郎=徳富蘆花訳述) eBOOK
「警文学者」(人見一太郎)
「国民的大問題」(人見一太郎) eBOOK
「傾城枕獅子(改題/春興鏡獅子)」(福地源一郎=福地桜痴) eBOOK
「芭蕉雑談」(正岡子規) eBOOK
「鈍機翁冒険譚」(松居松葉抄訳/セルバンテス『ドン・キホーテ』)
eBOOK(上) eBOOK(下) eBOOK2
「最暗黒の東京」(松原二十三階堂=松原岩五郎=乾坤一布衣) eBOOK
「獄中の働」(丸亭素人訳) eBOOK
「三人探偵」(丸亭素人訳) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「文庫」(南新二)
「荻生徂徠」(山路愛山) eBOOK
明治27年(1894年)
「義血侠血」(泉鏡花) eBOOK
「日本昔噺」(厳谷小波)
「文学者となる法」(三文字屋金平=内田魯庵) eBOOK
「林中之罪(一名・血錆の十字架)」(菊亭笑庸訳) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「三人やもめ」(北田薄氷) eBOOK
「知られぬ日本の面影」(小泉八雲) eBOOK
「久知那志の花」(小出粲)
「夢幻」(小宮山天香)
「仇娘呉服屋騒動」(彩霞園柳香) eBOOK
「隔屏物語」(堺利彦)
「湖上之美人」(塩井雨江訳/スコット『湖上の美人』)
「日本風景論」(志賀重昴)
「瀧口入道」(高山樗牛) eBOOK
「桐一葉」(坪内逍遙) eBOOK
「社会主義一班」(長澤別天)
「俄長者」(中村花痩)
「曇天」(原抱一庵)
「明月」(原抱一庵)
「大つごもり」(樋口一葉) eBOOK
「畜生塚」(広津柳浪) eBOOK
「侠客春雨傘」(福地桜痴) eBOOK
「朝鮮宮中物語 張嬪」(福地桜痴)
「男やもめ」(前田曙山)
「昇旭朝鮮太平記」(松居松翁=松葉)
「新井白石」(山路愛山) eBOOK
「亡国の音」(与謝野鉄幹)
明治28年(1895年)
「陸眼八目」(飯田旗郎訳/ピエール・ロチ『秋の日本』) eBOOK
「外科室」(泉鏡花) eBOOK
「夜行巡査」(泉鏡花) eBOOK
「国語のため」(上田万年) eBOOK
「余は如何にして基督信徒となりし乎」(内村鑑三)
「電光石火」(江見水蔭)
「女房殺し」(江見水蔭) eBOOK
「青葡萄」(尾崎紅葉) eBOOK
「菊水」(長田秋濤) eBOOK
「書記官」(川上眉山) eBOOK
「改良若殿」(小杉天外)
「連俳小史」(佐々政一=佐々醒雪) eBOOK
「医学修業」(田沢稲舟)
「しろばら」(田沢稲舟)
「逍遥遺稿」(中野逍遥) eBOOK(正編)
「十三夜」(樋口一葉) eBOOK
「たけくらべ」(樋口一葉) eBOOK
「にごりえ」(樋口一葉) eBOOK
「ゆく雲」(樋口一葉) eBOOK
「亀さん」(広津柳浪) eBOOK
「黒蜴■(虫偏に廷)(くろとかげ)」(広津柳浪) eBOOK
「変目伝」(広津柳浪) eBOOK
「人柱築島由来」(藤野古白) eBOOK
「蝗うり」(前田曙山)
「俳諧大要」(正岡子規) eBOOK
「自然児」(宮崎湖処子) eBOOK
「鳰の浮巣」(宮崎三昧) eBOOK
「壮士の犯罪」(本吉欠伸) eBOOK
明治29年(1896年)
「照葉狂言」(泉鏡花) eBOOK
「西洋 仙郷奇談」(井上寛一訳・矢野龍渓補/ペロー、ヴィルヌーヴ夫人、ボーモン夫人、ミュラ伯爵夫人著) eBOOK
「紫宸殿」(岡本綺堂)
「亀甲鶴」(小栗風葉) eBOOK
「多情多恨」(尾崎紅葉) eBOOK
「断末魔」(桐生悠々)
「六人の死骸」(黒岩涙香) eBOOK
「心」(小泉八雲)
「闇のうつつ」(後藤宙外) eBOOK
「三人冗語」(脱天子=幸田露伴・登仙坊=斎藤緑雨・鐘礼舎=森鴎外) eBOOK
「雲中語」(幸田露伴・斎藤緑雨・森鴎外・依田学海・饗庭篁村・森田思軒・尾崎紅葉) eBOOK
「破れ羽織」(堺枯川=利彦) eBOOK
「美文韻文花紅葉」(塩井雨江・大町桂月・武島羽衣)
「局松島」(武田仰天子) eBOOK
「五大堂」(田沢稲舟) eBOOK
「峯の残月」(田沢稲舟・山田美妙)
「牧の方」(坪内逍遥) eBOOK
「藪柑子」(徳田秋声)
「Seen and Unseen」(野口米次郎)
「ふたすぢ道」(長谷川胡恋=長谷川如是閑)
「うらむらさき」(樋口一葉) eBOOK
「この子」(樋口一葉) eBOOK
「わかれ道」(樋口一葉) eBOOK
「われから」(樋口一葉) eBOOK
「浅瀬の波」(広津柳浪) eBOOK
「今戸心中」(広津柳浪) eBOOK
「河内屋」(広津柳浪) eBOOK
「松蘿玉液」(正岡子規) eBOOK
「社会百方面」(乾坤一布衣=松原二十三階堂=岩五郎) eBOOK
「征塵余禄」(松原二十三階堂=岩五郎)
「うすくちびる」(水谷不倒)
「さびがたな」(水谷不倒)
「当世五人男」(村上浪六) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「十五少年」(思軒居士=森田思軒訳/ヴェルヌ『二年間の休暇(十五少年漂流記)』) eBOOK
「神の裁判」(柳川春葉)
「東西南北」(与謝野寛=与謝野鉄幹) eBOOK
明治30年(1897年)
「従五位」(漣山人=巌谷小波・思案外史=石橋思案合作) eBOOK
「海の秘密」(江見水蔭) eBOOK
「金色夜叉」(尾崎紅葉) eBOOK
「ふところ日記」(川上眉山) eBOOK
「源おぢ」(国木田独歩) eBOOK
「仏土の落穂」(小泉八雲)
「若菜集」(島崎藤村) eBOOK
「しろあらし」(島村抱月) eBOOK
「日本主義を賛す」(高山樗牛)
「由井正雪」(塚原渋柿園) eBOOK
「The Voice of the Valley」(野口米次郎)
「畜生腹」(広津柳浪) eBOOK
「非国民」(広津柳浪) eBOOK
「大森彦七」(福地桜痴) eBOOK
「うき草」(長谷川辰之助=二葉亭四迷訳/ツルゲーネフ著) eBOOK
「俳人蕪村」(正岡子規) eBOOK
「怨めしや」(三宅青軒) eBOOK
「そめちがへ」(森鴎外) eBOOK
「白すみれ」(柳川春葉)
「紅筆」(山岸荷葉)
「天地玄黄」(与謝野寛=与謝野鉄幹) eBOOK
明治31年(1898年)
「くれの廿八日」(内田魯庵)
「黄菊白菊」(大町桂月)
「武蔵野」(国木田独歩) eBOOK
「忘れえぬ人々」(国木田独歩) eBOOK
「二日物語」(幸田露伴) eBOOK
「三人片輪」(竹柴其水) eBOOK
「不如帰」(徳富蘆花) eBOOK
「福翁自伝」(福沢諭吉) eBOOK
「にごり水」(前田曙山)
「歌よみに与ふる書」(正岡子規) eBOOK
「車上所見」(正岡子規)
「小園の記」(正岡子規) eBOOK
「埋れ井戸」(三島霜川)
「片恋源氏」(山岸荷葉)
「お才」(横瀬夜雨) eBOOK
明治32年(1899年)
「団扇太鼓」(生田葵山)
「湯島詣」(泉鏡花) eBOOK
「己が罪」(菊池幽芳) eBOOK(前編) eBOOK(中編) eBOOK(後編) eBOOK2
「狼少年(ジャングルブック)」(黒田湖山訳/キップリング著) eBOOK
「一国の首都」(幸田露伴) eBOOK
「扇頭小景」(小泉烏水)
「蛇いちご」(小杉天外) eBOOK
「腐肉団」(後藤宙外) eBOOK
「嶺雲揺曳」(田岡嶺雲) eBOOK(第二)
「半日あるき」(高浜虚子)
「ふるさと」(田山花袋)
「天地有情」(土井晩翠) eBOOK
「薄衣」(永井荷風) eBOOK
「骨ぬすみ」(広津柳浪) eBOOK
「もつれ糸」(広津柳浪)
「女大学評論 新女大学」(福沢諭吉) eBOOK
「千枚張(改題/腕くらべ)」(前田曙山) eBOOK
「悪源太」(松居松翁=松葉)
「行路心」(柳川春葉)
「夕月」(横瀬夜雨)
「日本之下層社会」(横山源之助) eBOOK
明治33年(1900年)
「馬加物語」(淡島寒月)
「高野聖」(泉鏡花) eBOOK
「鉄道唱歌」(大和田建樹) eBOOK
「海国冒険奇譚 海底軍艦」(押川春浪) eBOOK
「郊外」(国木田独歩) eBOOK
「初恋」(国木田独歩) eBOOK
「戦塵」(久留島武彦)
「太郎坊」(幸田露伴) eBOOK
「はつ姿」(小杉天外) eBOOK
「雲のゆくへ」(徳田秋声) eBOOK
「思出の記」(徳富健次郎=徳富蘆花) eBOOK
「自然と人生」(徳富健次郎=徳富蘆花) eBOOK
「武士道」(新渡戸稲造) eBOOK(櫻井鴎村訳)
「聖人か盗賊か」(省庵居士=原抱一庵訳/リットン著)
「目黒小町」(広津柳浪)
「さんど笠」(前田曙山)
「朝嵐夕雨」(丸岡桂・田口春塘)
「夕汐」(三島霜川)
「鎗一筋」(村井弦斎) eBOOK
「夢の夢」(柳川春葉) eBOOK
「裁縫指南所」(山岸荷葉)
明治34年(1901年)
「註文帳」(泉鏡花) eBOOK
「破垣」(内田魯庵)
「歌集 片われ月」(金子薫園) eBOOK
「無弦弓」(河井醉茗) eBOOK
「女詩人」(草村北星) eBOOK
「牛肉と馬鈴薯」(国木田独歩) eBOOK
「史外史伝 巌窟王」(黒岩涙香訳/デュマ著) eBOOK(巻之一) eBOOK(巻之二) eBOOK(巻之三) eBOOK(巻之四)
eBOOK2(上巻) eBOOK2(下巻)
「廿世紀之怪物帝国主義」(幸徳秋水)
「美文韻文 暗香疎影」(塩井雨江) eBOOK
「落梅集」(島崎藤村) eBOOK
「ゆく春」(薄田泣菫) eBOOK
「美的生活を論ず」(高山樗牛) eBOOK
「人の罪」(田口掬汀)
「行く秋」(谷活東)
「桃の井橋」(谷活東)
「野の花」(田山花袋) eBOOK
「暁鐘」(土井晩翠) eBOOK
「難破船」(中内蝶二)
「一年有半」(中江兆民) eBOOK
「無花果」(中村春雨=中村吉蔵) eBOOK
「迦具土(かぐづち)」(服部躬治) eBOOK
「最近国家社会主義」(久松義典) eBOOK
「社会小説東洋社会党」(久松義典)
「桧舞台」(前田曙山) eBOOK
「嗚呼売淫国」(正岡芸陽)
「時代思想の権化 星亨と社会」(正岡芸陽) eBOOK
「婦人の側面」(正岡芸陽) eBOOK
「仰臥漫録」(正岡子規)
「墨汁一滴」(正岡子規) eBOOK
「探偵小説 紫美人」(松居松葉) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「錦木」(柳川春葉)
「紺暖簾」(山岸荷葉) eBOOK
「みだれ髪」(与謝野晶子) eBOOK
「紫」(与謝野鉄幹)
「小百合集」(吉野甫=吉野臥城) eBOOK
「堀の小梅」(渡辺黙禅)
明治35年(1902年)
「夜の人」(井上唖々)
「社会百面相」(内田魯庵) eBOOK
「東洋の理想」(岡倉天心)
「濱子」(草村北星) eBOOK
「酒中日記」(国木田独歩) eBOOK
「運命論者」(国木田独歩) eBOOK
「空知川の岸辺」(国木田独歩) eBOOK
「大学攻撃」(黒田湖山) eBOOK
「はやり唄」(小杉天外) eBOOK
「めぐる泡」(後藤宙外)
「うもれ咲」(小林蹴月)
「しらぬ火」(篠原温亭)
「旧主人」(島崎藤村) eBOOK
「新美辞学」(島村瀧太郎=島村抱月) eBOOK
「公孫樹下にたちて」(薄田泣菫) eBOOK
「重右衛門の最後」(田山花袋) eBOOK
「侠足袋」(塚原渋柿園) eBOOK
「春光」(徳田秋声)
「黒潮」(徳富健次郎=徳富蘆花) eBOOK(第一篇)
「あらひ髪」(登張信一郎=登張竹風) eBOOK
「地獄の花」(永井荷風) eBOOK
「野心」(永井荷風) eBOOK
「日本少女のアメリカ日記」(野口米次郎)
「ほし草」(橋本忠夫=橋本青雨)
「新思潮とは何ぞや」(長谷川天渓) eBOOK
「雨」(広津柳浪) eBOOK
「山菅」(星野天知) eBOOK
「女流ハイカラー」(正岡芸陽)
「英雄主義」(正岡芸陽) eBOOK
「偽善百方面」(正岡芸陽)
「病牀六尺」(正岡子規) eBOOK
「小説 自由結婚」(三島才二=三島霜川・徳田秋声) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「聖書婦人」(三島霜川)
「現世相」(水谷不倒) eBOOK(後編)
「三十三年の夢」(宮崎滔天) eBOOK
「秋袷」(柳川春葉)
「伊勢の海」(柳田国男)
「新社会」(矢野龍渓) eBOOK
「雌蝶雄蝶」(山岸荷葉)
「埋木」(与謝野鉄幹)
明治36年(1903年)
「悪縁」(稲岡奴之助) eBOOK
「恋の短銃〈ピストル〉」(大沢天仙) eBOOK
「観音岩」(川上眉山) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「独絃哀歌」(蒲原有明) eBOOK
「家庭小説 乳姉妹」(菊池幽芳) eBOOK(前編) eBOOK(後編) eBOOK2
「脚本 こころ」(北里闌) eBOOK
「一夜夫婦」(木村錦之助=木村錦花) eBOOK
「天人論」(黒岩周六=黒岩涙香) eBOOK
「耳なし芳一」(小泉八雲) eBOOK
「雁坂越」(幸田露伴) eBOOK
「天うつ浪」(幸田露伴) eBOOK(第一巻) eBOOK(第二巻) eBOOK(第三巻)
「社会主義神髄」(幸徳秋水) eBOOK
「魔風恋風」(小杉天外) eBOOK(前編)
「社会主義詩集」(児玉花外)
「紀念小著苅萱集」(齋藤弔花) eBOOK
「国家と詩人」(齋藤野の人) eBOOK
「おもひ草」(佐佐木信綱) eBOOK
「二年越」(温亭主人=篠原温亭) eBOOK
「江戸城明渡」(高安三郎=高安月郊) eBOOK
「新生涯」(田口掬汀) eBOOK
「美文韻文霓裳微吟」(武島羽衣)
「神秘」(武林無想庵)
「桎梏」(徳田秋声)
「小説 夢の女」(永井荷風) eBOOK
「From the Eastern Sea」(野口米次郎) eBOOK
「ささやき」(藤沢古雪=藤沢周次) eBOOK
「理想の女学生」(正岡芸陽) eBOOK
「食道楽」(村井弦斎) eBOOK(縮刷版)
「仮寝姿」(森田草平) eBOOK
「忘れ水」(柳川春葉)
「五人娘」(山岸荷葉) eBOOK
「失恋境」(山岸荷葉) eBOOK
明治37年(1904年)
「和蘭皿」(生田葵山) eBOOK
「日本の覚醒」(岡倉天心)
「萩之家遺稿」(落合直文) eBOOK
「銀鈴」(尾上柴舟) eBOOK
「火の柱」(木下尚江) eBOOK
「良人の自白」(木下尚江) eBOOK(上) eBOOK(中) eBOOK(下) eBOOK(続)
「相思怨」(草村北星) eBOOK
「怪談」(小泉八雲)
「東京の木賃宿」(幸徳秋水) eBOOK
「共産党宣言」(幸徳秋水・堺利彦訳/マルクス・エンゲルス著) eBOOK
「家庭小説 女夫波」(田口掬汀) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「女郎蜘」(谷活東)
「露骨なる描写」(田山花袋)
「新曲浦島」(坪内逍遥) eBOOK
「帰朝の記」(野口米次郎) eBOOK
「妾の半生涯」(福田英子) eBOOK
「天才の失恋」(正岡芸陽) eBOOK
「竹の里歌」(正岡子規) eBOOK
「寂寞」(正宗白鳥) eBOOK
「妻木」(松瀬青々) eBOOK
「大塊一塵」(三宅雪嶺) eBOOK
「北海熊」(行友李風) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「君死に給ふことなかれ」(与謝野晶子)
「小扇」(与謝野晶子) eBOOK
「毒草」(与謝野晶子・与謝野鉄幹) eBOOK
明治38年(1905年)
「あこがれ」(石川啄木) eBOOK
「野菊の墓」(伊藤左千夫) eBOOK
「海潮音」(上田敏訳) eBOOK
「琵琶歌」(大倉桃郎) eBOOK
「お百度詣」(大塚楠緒子) eBOOK
「霰に霙」(小川未明) eBOOK
「青春」(小栗風葉) eBOOK(後編)
「小野のわかれ」(小山内薫) eBOOK
「水彩色」(加藤眠柳) eBOOK
「春鳥集」(蒲原有明) eBOOK
「露子夫人」(草村北星)
「まひる野」(窪田空穂) eBOOK
「二十五絃」(薄田泣菫) eBOOK
「桜時雨」(高安三郎=高安月郊) eBOOK
「伯爵夫人」(田口掬汀) eBOOK(前編) eBOOK(後編) eBOOK(終編)
「悲劇竹村翠」(武林無想庵)
「第二軍従征日記」(田山花袋) eBOOK
「予が見神の実験」(綱島梁川) eBOOK
「団栗」(寺田寅彦) eBOOK
「竜舌蘭」(寺田寅彦) eBOOK
「幻影の盾」(夏目漱石) eBOOK
「倫敦塔」(夏目漱石) eBOOK
「吾輩は猫である」(夏目漱石) eBOOK
「海潮音」(長谷川時雨)
「国文学全史平安朝篇」(藤岡作太郎)
「わらはの思ひ出」(福田英子)
「夏花少女」( (前田儀作=前田林外) eBOOK
「新体詩集 夏廂」(正富汪洋) eBOOK
「人の心」(町田柳塘=楓村居士)
「エルナニ」(松居松翁=松葉翻案/ユーゴー著)
「夏姫」(三木露風)
「牢獄」(三島霜川)
「泊客」(柳川春葉) eBOOK
「上杉謙信」(山崎紫紅) eBOOK
「花守」(横瀬夜雨) eBOOK
「恋衣」(与謝野晶子・山川登美子・茅野[増田]雅子) eBOOK
「小松嵐」(渡辺黙禅) eBOOK(前編)
明治39年(1906年)
「孔雀船」(伊良子清白) eBOOK
「神秘的半獣主義」(岩野泡鳴) eBOOK eBOOK2
「茶の本」(岡倉覚三=岡倉天心) eBOOK
「麗子夫人」(小栗風葉) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「新浮世風呂」(海賀変哲) eBOOK
「三千里」(河東碧梧桐) eBOOK
「噫無情」(黒岩涙香訳/ユゴー『レ・ミゼラブル』) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「ゆく雲」(児玉花外) eBOOK
「小説 ゑはがき帖」(小林蹴月) eBOOK
「少女の煩悶」(齋藤弔花) eBOOK
「肉弾」(桜井忠温) eBOOK
「あん火」(佐藤紅緑) eBOOK
「朝飯」(島崎藤村) eBOOK
「破戒」(島崎藤村) eBOOK
「囚はれたる文芸」(島村抱月) eBOOK
「白羊宮」(薄田泣菫) eBOOK
「葛城の神」(薄田泣菫)
「千鳥」(鈴木三重吉) eBOOK
「その雫」(武林無想庵)
「天草一揆」(塚原渋柿園) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「小説 新気運」(中島孤島) eBOOK
「炭焼のむすめ」(長塚節) eBOOK
「盲巡礼」(中村星湖)
「すひかつら」(中谷無涯) eBOOK
「草枕」(夏目漱石) eBOOK
「坊つちゃん」(夏目漱石) eBOOK
「二百十日」(夏目漱石) eBOOK
「其面影」(二葉亭四迷) eBOOK
「猫文士気焔録」(藤代素人=藤代禎輔) eBOOK
「花妻」(前田林外) eBOOK
「二階の窓」(正宗白鳥) eBOOK
「残灰」(三島霜川)
「舞姫」(与謝野晶子) eBOOK
「夢の華」(与謝野晶子) eBOOK
明治40年(1907年)
「淡潮」(石丸梅外=石丸梧平) eBOOK
「婦系図」(泉鏡花) eBOOK
「夜」(岡本霊華)
「静夜」(尾上柴舟) eBOOK
「鴎心録」(角田勤一郎=浩々歌客) eBOOK
「無解決の文学」(片山伸)
「塵溜(塵塚)」(川路柳虹)
「天風魔帆」(児玉花外)
「滝の音」(小林蹴月) eBOOK
「湖畔の悲歌」(沢村胡夷)
「駅夫日記」(白柳秀湖) eBOOK
「お三津さん」(鈴木三重吉) eBOOK
「山彦」(鈴木三重吉) eBOOK
「風流懺法」(高浜虚子) eBOOK
「競馬」(武田仰天子)
「蒲団」(田山花袋) eBOOK
「少女病」(田山花袋) eBOOK
「少年行」(中村星湖)
「天狗廻状」(半井桃水)
「虞美人草」(夏目漱石) eBOOK
「縁」(野上彌生子)
「平凡」(二葉亭四迷) eBOOK
「立志小説 全力の人」(堀内新泉) eBOOK(前編) eBOOK(後編) eBOOK2
「紅塵」(正宗白鳥) eBOOK
「妖怪画」(正宗白鳥) eBOOK
「探検小説 空中軍艦」(町田柳塘=楓村居士)
「第一人者」(真山青果) eBOOK
「南小泉村」(真山青果) eBOOK
「茗荷畠」(真山青果) eBOOK eBOOK2
「厩の馬」(三島霜川)
「解剖室」(三島霜川) eBOOK
「孤独」(三島霜川)
「二十八宿」(横瀬夜雨) eBOOK
「家庭小説 処女の秘密」(大木臥葉・吉野臥城) eBOOK
「家庭小説 もつれ縁」(吉野臥城) eBOOK
「大石内蔵助」(緑園生=渡辺霞亭) eBOOK
「炎の柱」(和辻哲郎)
明治41年(1908年)
「鳥影」(石川啄木) eBOOK
「隣の嫁」(伊藤左千夫) eBOOK
「春の潮」(伊藤左千夫) eBOOK
「闇の盃盤」(岩野泡鳴) eBOOK
「世間師」(小栗風葉) eBOOK
「小説 灰燼」(上司小剣) eBOOK
「有明集」(蒲原有明) eBOOK
「竹の木戸」(国木田独歩) eBOOK
「長者星」(小杉天外) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「小説 榾」(佐藤紅緑) eBOOK
「網走まで」(志賀直哉)
「荒絹」(志賀直哉)
「或る朝」(志賀直哉)
「速夫の妹」(志賀直哉)
「春」(島崎藤村) eBOOK
「文芸上の自然主義」(島村瀧太郎=島村抱月) eBOOK
「痩犬」(相馬御風)
「鶏頭」(高浜虚子) eBOOK
「俳諧師」(高浜虚子) eBOOK
「生」(田山花袋) eBOOK
「妻」(田山花袋) eBOOK
「障子の落書」(藪柑子=寺田寅彦) eBOOK
「欧米紀遊 二万三千哩」(戸川秋骨) eBOOK
「新世帯」(徳田秋声) eBOOK
「あめりか物語」(永井荷風) eBOOK
「萩のしつく」(中島歌子)
「半生」(中村星湖) eBOOK
「坑夫」(夏目漱石) eBOOK
「三四郎」(夏目漱石) eBOOK
「夢十夜」(夏目漱石) eBOOK
「現実暴露の悲哀」(長谷川天渓) eBOOK
「元禄快挙録」(福本日南) eBOOK
「明日」(正宗白鳥) eBOOK
「五月幟」(正宗白鳥) eBOOK
「何処へ」(正宗白鳥) eBOOK
「二家族」(正宗白鳥) eBOOK
「新春夏秋冬」(松根東洋城)
「生れざりしならば」(真山青果) eBOOK
「癌腫」(真山青果) eBOOK
「奔流」(真山青果)
「餌拾」(三島霜川)
「おみよ」(水野葉舟)
「響」(水野葉舟) eBOOK
「立志小説 独立独行」(吉野臥城・大木臥葉) eBOOK
「栗の花」(吉野左衛門)
「海の声」(若山牧水) eBOOK
「女ざむらひ」(渡辺黙禅) eBOOK
明治42年(1909年)
「江戸か東京か」(淡島寒月) eBOOK
「耽溺」(岩野泡鳴) eBOOK
「社会進化論」(小山鼎浦)
「南北」(小栗風葉・真山青果)
「邪宗門」(北原白秋) eBOOK
「悪戯小僧日記」(佐々木邦) eBOOK
「大役小志」(志賀重昂) eBOOK
「懐疑と告白」(島村抱月) eBOOK
「近代文芸之研究」(島村瀧太郎=島村抱月) eBOOK
「三畳と四畳半」(高浜虚子) eBOOK
「続俳諧師」(高浜虚子) eBOOK
「北米の花」(田村松魚) eBOOK
「田舎教師」(田山花袋) eBOOK
「狐」(永井荷風) eBOOK
「ふらんす物語」(永井荷風) eBOOK(新編)
「氷の花」(中里介山)
「それから」(夏目漱石) eBOOK
「月雪花」(芳賀矢一) eBOOK
「?(改題/額の男)」(長谷川如是閑) eBOOK
「地獄」(正宗白鳥) eBOOK
「廃園」(三木露風) eBOOK
「落伍者」(三島霜川)
「徒労」(水野仙子)
「悪夢」(水野盈太郎=水野葉舟) eBOOK
「微温」(水野葉舟)
「奇絶怪絶、飛来の短剣」(三津木春影訳/フリーマン「アルミニウムの短剣」) eBOOK
「花の趣味」(三宅花圃) eBOOK
「ヰタ・セクスアリス」(森鴎外) eBOOK
「半日」(森鴎外) eBOOK
「金貨」(森鴎外) eBOOK
「煤煙」(森田草平) eBOOK
「緑雲」(吉江喬松)
「女ざむらひ」(渡辺黙禅) eBOOK
明治43年(1910年)
「虻」(青木健作) eBOOK
「一握の砂」(石川啄木) eBOOK
「時代閉塞の現状」(石川啄木) eBOOK
「歌行燈」(泉鏡花) eBOOK
「出雲の阿国」(伊原青々園) eBOOK
「うづまき」(上田敏) eBOOK
「自己主張の思想としての自然主義」(魚住折蘆)
「身替座禅」(岡村柿紅)
「恭三の父」(加能作次郎) eBOOK
「路傍の花」(川路柳虹) eBOOK
「松山一家」(郡虎彦)
「剃刀」(志賀直哉)
「家」(島崎藤村) eBOOK(上) eBOOK(下)
「養家」(白石実三)
「小鳥の巣」(鈴木三重吉) eBOOK(上) eBOOK(下)
「外相夫人」(田口掬汀)
「刺青」(谷崎潤一郎) eBOOK
「麒麟」(谷崎潤一郎) eBOOK
「縁」(田山花袋) eBOOK
「別れたる妻に送る手紙」(近松秋江) eBOOK
「NAKIWARAI」(土岐哀果=土岐善麿) eBOOK
「紅茶の後」(永井荷風) eBOOK
「高野の義人」(中里介山) eBOOK
「土」(長塚節) eBOOK
「門」(夏目漱石) eBOOK
「万年筆」(長谷川天渓) eBOOK
「収穫」(前田夕暮) eBOOK
「米国野球見物」(正岡芸陽) eBOOK
「徒労」(正宗白鳥) eBOOK
「微光」(正宗白鳥) eBOOK
「寂しき曙」(三木露風) eBOOK
「娘」(水野仙子) eBOOK
「青年」(森鴎外) eBOOK
「あだ花」(森しげ) eBOOK
「石神問答」(柳田国男) eBOOK
「遠野物語」(柳田国男) eBOOK
「明治富豪史」(横山源之助)
「礼厳法師歌集」(与謝野礼厳(尚絅)著・与謝野鉄幹編) eBOOK eBOOK2
「酒ほがひ」(吉井勇) eBOOK
「別離」(若山牧水) eBOOK(上巻) eBOOK(下巻)
明治44年(1911年)
「或る女」(有島武郎) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「修禅寺物語」(岡本綺堂) eBOOK
「薔薇と巫女」(小川未明) eBOOK
「大川端」(小山内薫) eBOOK
「厄年」(加能作次郎) eBOOK
「思ひ出」(北原白秋) eBOOK
「炉辺」(窪田空穂) eBOOK
「基督抹殺論」(幸徳秋水) eBOOK
「濁った頭」(志賀直哉)
「千曲川のスケッチ」(島崎藤村) eBOOK
「墓穴」(白石実三)
「歴史小説明智光秀」(武田仰天子) eBOOK
「書斎より街頭に」(田中王堂) eBOOK
「少年」(谷崎潤一郎) eBOOK
「乱調子」(田村松魚)
「あきらめ」(田村とし子=田村俊子) eBOOK
「芸者」(田村西男) eBOOK
「髪」(田山花袋) eBOOK
「黴」(徳田秋声) eBOOK
「スヰートホーム」(内藤千代子) eBOOK
「澪」(長田幹彦) eBOOK
「善の研究」(西田幾多郎) eBOOK
「父親と三人の娘」(野上彌生子)
「夜の舞踏」(人見東明) eBOOK
「元始女性は太陽であつた」(平塚らいてう) eBOOK
「嘘つく女」(深尾葭汀) eBOOK
「泥人形」(正宗白鳥) eBOOK
「樹蔭(樹陰)」(松本泰) eBOOK
「壁画」(水野葉舟)
「嵐」(水上滝太郎) eBOOK
「山の手の子」(阿部省三=阿部肖三=水上滝太郎) eBOOK
「お目出たき人」(武者小路実篤) eBOOK
「桃色の室」(武者小路実篤)
「雁」(森鴎外) eBOOK
「妄想」(森鴎外) eBOOK
「自叙伝」(森田草平)
「初恋」(森田草平) eBOOK
「科学と人生」(柳宗悦) eBOOK
「新人国記」(横山健堂) eBOOK
「午後三時」(吉井勇) eBOOK
明治45年(1912年)
「お絹」(青木健作) eBOOK
「最近の小説家」(生田長江) eBOOK
「悲しき玩具」(石川啄木) eBOOK
「魯鈍な猫」(小川未明) eBOOK
「家なき児」(菊池幽芳訳/マロ『家なき子』) eBOOK(前編) eBOOK(後編)
「和泉屋染物店」(木下杢太郎) eBOOK
「近代文学十講」(厨川白村) eBOOK
「努力論」(幸田露伴) eBOOK
「道成寺」(郡虎彦) eBOOK
「哀花熱花」(兒玉傅八=兒玉花外) eBOOK
「下町」(後藤末雄)
「平家の人々」(高須梅渓=高須芳次郎) eBOOK
「悪魔」(谷崎潤一郎) eBOOK eBOOK(続編)
「誓言」(田村俊子) eBOOK
「渦」(田山花袋) eBOOK
「零落」(長田幹彦) eBOOK
「彼岸過迄」(夏目漱石) eBOOK
「巣鴨の女」(野上臼川=野上豊一郎) eBOOK
「秋の一日」(野上彌生子)
「テレジヤのかなしみ」(野上彌生子)
「毒の園」(昇曙夢訳/ソログーブ作)
「春のゆめ」(福田夕咲)
「生霊」(正宗白鳥) eBOOK
「白壁」(正宗白鳥) eBOOK
「偶像」(水野葉舟)
「森」(水野葉舟)
「世間知らず」(武者小路実篤)
「かのやうに」(森鴎外) eBOOK
「兄と妹」(守田有秋) eBOOK
「生さぬ仲」(柳川春葉) eBOOK
「雲のいろいろ」(与謝野晶子)
|
|
|
|
●作品レビュー
『金之助之話』(前田夏繁=前田香雪/明治9年11月~?)
※「東京絵入新聞」に実際に連載されたのは、明治11年8月21日~9月11日といわれる。
(レビュー未/以下は大曲駒村「明治時代の絵入新聞と其挿絵担任浮世絵師」<書物展望 昭和11年10月号>より抜粋)
「平仮名絵入新聞」は、翌九年三月一日から「東京絵入新聞」と改題し、前田香雪が才筆を馳せる一方、例に依って芳幾が其の挿絵を担任して居たが、その年の十一月に香雪の「金之助之話」と云ふが連載される事となつて、一層世の賞讃を博した。これは元より虚実混合の読み物で、作品としては何等評す可き価値のあるものではなかつたが、新聞が単なる時事報道の外に所謂「続き物」てふ読物を連載し出した濫觴で、後の新聞小説の淵源を為すものとして特筆すべきものであつた。云ふまでもなく、芳幾はこれに挿絵を画き、画者として作者同様の評判を贏ち得た。これはまた、新聞小説挿絵の嚆矢と云ふを得るものである。
(以下は高木文 著「高木文随筆 その一 明治全小説戯曲大観」<聚芳閣/大正14年11月>より抜粋)
九年に絵入新聞に前田夏繁の金之助之話と題する小説が連載された、之が新聞小説の初めで漸く其気運に向つて来た。
(以下は中島河太郎 著「日本推理小説史 第1巻」<桃源社/1964年>より抜粋)
新聞小説の起原は、前田香雪の「金之助の話」で明治九年のことといわれるが、実際の新聞にあたった蛯原八郎氏によれば十一年八月である。そうすれば久保田彦作の「鳥追いお松の伝」が、「かなよみ」紙に載りはじめたのが、明治十年十二月だから、これがもっとも早いものとなる。
いわゆる「つづきもの」の祖としては、「金之助の話」でも「鳥追いお松の伝」でもなく、「岩田八十八の話」が挙げられることが多い。
(以下は高木健夫「新聞小説史稿 一」<三友社/昭和39年>より抜粋)
明治八年十一月二十七日『郵便報知新聞』が、ある裁判言渡書を掲載した。これは裁判所の書類の様式そのままのもので、長くて読みづらくて、どうにもならないものだが、しかし、こういう風に記事を扱うのが、大新聞のならわしなのであった。
ところが、大新聞が、しちむずかしい判決文をそのままうのみにして掲載した材料を馬琴風のロマンに変作したのが、『平仮名絵入新聞』の香雪・前田健次郎である。…
…『郵便報知』が、長ったらしい裁判言渡書を掲載した翌十一月二十八日、『平仮名絵入』は、同じ言渡書の内容を「岩田八十八の話」と題して三日間連載して読者の興味をひいた。…
…前田香雪は、一日一日を読者に気を持たせ、フィクションを加えて書きつづけたので、「小説」というものを知らぬ読者は、フィクションをそのまま事実と思いこみ、「それからどうした」「みつはどこへ行ったか」などという問い合せが続出して主筆藍泉を苦笑させ、同時にこのようなニュース読み物が、いかに読者の興味をつなぐか、ということを新聞製作者自身にも思いいたらせた。
これが、いわば「新聞小説」の原型であり、またそもそものはじめとみるべき連載読み物の第一号と考えられる。
前田香雪(1841-1916)
天保12年正月6日江戸に生まれる。国学者前田夏蔭の子。名は夏繁、通称健次郎。
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『鳥追阿松海上新話』(久保田彦作/明治10年12月~明治11年1月)
明治10年12月10日より『仮名読新聞』にて「鳥追お松の伝」のタイトルで連載開始。
いわゆる「毒婦もの」で、初めて新聞に連載された作品。
毒婦ものは、明治初期より大ブームとなり、『新編明治毒婦伝』(金星堂)など数多くの書籍が刊行されている。
『新編明治毒婦伝』(金星堂/明治19年)収録作品
岡本勘造「夜嵐於衣花廼仇夢(よあらしおきぬはなのあだゆめ)」
仮名垣魯文「高橋阿伝夜刃譚(たかはしおでんやしゃものがたり)」
伊藤専三「引眉毛権妻於辰(ひきまゆげごんさいおたつ)」
土屋南翠「茨木阿瀧紛白糸(いばらきおたきみだれのしらいと)」
久保田彦作「鳥追阿松海上新話(とりおいおまつかいじょうしんわ)」
伊藤専三「鳴渡雷神於新(なりわたるかみなりおしん)」
久保田彦作(1846-1898)
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『新未来記』(近藤真琴訳/明治11年12月)
明治7年に出された上條信次訳「開化進歩 後世夢物語」と同一原書を訳したもの。原書は、ペーター・ハルティンクが1865年にジオスコリデス(Dr.Dioscoordis)名義で刊行した『西暦2065年』。
訳者曰く、本書は10年前(慶応4年)に訳述したとあり、「開化進歩 後世夢物語」よりも早い。
(レビュー未/以下は本書巻頭にある例言より抜粋)
原書ハ紀元二千六十五年ト題シ又未来ノ瞥見ト云フ和蘭ノ博士「ジヲスコリデス」ノ著ト記ス三百年来学術次第ニ進ミ人生ノ状昔日ニ異ナルヲ以テ推シテ二百年ノ後ヲ想像シ夢ニ託シテ之レヲ記スル者ナリ今之レヲ訳スルニ稗史ノ体ニ擬スル者ハ城山肥田君ノ嘱ニ依リ看客ノ倦マザランコトヲ欲シテナリ
近藤真琴(1831-1886)
天保2年、志摩鳥羽藩士近藤儀智の二男として生誕。幼名は鉚之助。文久3年(1863年)には、現在の四谷に蘭学塾(攻玉社)を開設。森有礼、福澤諭吉、新島襄らとともに、明治六大教育家の一人とされる。
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『西洋滑稽 三笑人』(山田保抄訳/明治12年5月)
(レビュー未/以下は本書巻頭にある緒言より抜粋)
此書は仏蘭西にて、開板したる、滑稽借家の奇談を訳したる者にして、書中に挙る人名等は、彼国の言葉をそのまま用うるも、害なきことなれど、西洋の書を学ばざる人々は、しばしばこれを繰返しても、なお読み苦しき所あらんかと思ひ、其名を甚六又は野呂吉など、改めて、ひたすら婦女子の分り易きやうに物せるなり、かつ原書は長き物語にて、紙数も多分にあれど、其中我国の人情に合はずして、面白からぬ所は大抵削り去り、なるたけ興ある所のみを摘訳して、此一冊となしたるなれば、看官其心得にて読みもし、笑ひもしたまひて、日永の鬱を散ぜられんことを望むになん、
本書再版の奥付に、
訳者 東京府士族 山田保
出版人 東京府平民 早川新三郎
とあり、時代を感じる。(2023.11.24/菅井ジエラ)
山田保( - )
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『一滴千金 憂世の涕涙』(宮崎夢柳訳/明治17年3月)
エドワード・キング(Edward King)著。
(レビュー未/以下はAmazonの紹介ページより抜粋)
ネイティヴ・アメリカンの青年と銀行頭取令嬢の恋愛と革命。板垣退助が外遊から持ち帰った本を宮崎夢柳が訳した翻訳政治小説。
宮崎夢柳(1855-1889)
安政2年、土佐藩に生まれる。本名富要(とみやす)。別号芙蓉(ふよう)。『仏蘭西革命記 自由乃凱歌』(明治15年/自由新聞)、『虚無党実伝記 鬼啾啾』(明治17年/自由灯)、『芒の一と叢』(明治21年/東雲新聞)などを発表。一世を風靡した。
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『維廉得自由の一箭(ウヒルヘルムテルじいうのひとや)』(中川霞城訳/明治19年)
フリードリヒ・フォン・シラー(シルレル)著。
(レビュー未/以下は帝国印書会社出版発兌書目の広告文より抜粋)
霞城山人中川重麗君訳
●得廉得自由の一箭 全五冊
独逸の詩仙シルレル氏の作なる演劇を訳せられしものにて台詞の絶妙なるは英のセキスピヤに劣らず脚色の面白さは我忠臣蔵にも勝る傑作にして内外学士の序跋批評もあり有名なる俳優の詞文をも加へ文明国の演劇の親玉とも云ふべき書なり
※書名が「得廉得自由の一箭」と表記されている。未完。
※その後、実際には帝国印書会社からは出版されず(?)、明治23年に『少年文武』という少年雑誌に掲載された。
中川霞城(1850-1917)
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『欧洲小説 黄薔薇(こうしょうび)』(三遊亭円朝口述/明治20年1月)
明治20年1月「東京絵入新聞」掲載。同年4月、金星堂より刊行。
長らく、原著者不明、フランスの小説『毒婦ジュリアの物語』の翻案とされていたが、「円朝全集」を刊行する岩波書店が、2022年9月に「円朝『黄薔薇』原作梗概ならびに若干の考察」という論文を発表し、デュマ・フィスの“Le roman d’une femme”が原作と目されるとした。
PDFファイル 森裕介「円朝『黄薔薇』原作梗概ならびに若干の考察」
(レビュー未/以下は柳田泉「続随筆 明治文学」<春秋社/昭和13年>より抜粋)
明治十二年の十二月二十八日の有喜世新聞五九二号をみると、記事の中に、本日浅草井生村樓の忘年会で三遊亭円朝が「西洋人情ジユリヤの伝」というのをやるとなっている。この「ジユリヤの伝」とは何であろうか私はもちろんその時の話を聞いたのではないから、何ともいえないといえばいえないが、これは多分『黄薔薇』のことであろう。いな、確かにそうだと断言しても可いと思う。ジユリヤとは、『黄薔薇』の女主人公お嬢ジユリヤなる毒婦をさすものに違いないのである。そうすると『黄薔薇』は本になったのは明治二十年頃だとしても、講談としては少くなくとも明治十二年から巷間に伝わっていたものに違いない。
三遊亭円朝(1839-1900)
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『浮雲』(二葉亭四迷/第一篇 明治20年6月)
そもそも、結婚は種の繁栄のため、家の発展のためという大義があった。
本人同士の気持ち以上に、家族や周囲の人間たちの評価が影響力をもっていた。
明治に入って鎖国が終わり、世界と競争するために国家をあげての教育制度が導入される。
教育偏重主義によって、若者という存在が現れ注目されるようになる。
勉学に励み、未来を有望視される若者。
そんな周囲の期待と世間の評価とは裏腹に、若者たちには若者ならではの悩みが数多く生まれる。
知識と現実との差。恋愛もその一つだ。
明治に始まる近代小説は、結婚以前の恋愛過程を描き男女間の考え方の違いを克明に刻むようになる。
やがて、恋愛は大人がするもの、または権力者がするものという価値観を壊し、封建的な家制度を見直すことに繋がっていく。
内海文三は父親亡き後、東京に住む叔父の家に引き取られる。文三は叔父の庇護のもと、
勉学に励み卒業後役所での仕事を手に入れる。ところが、役所から解雇を言い渡されてしまうのだった。
力を持つ上司に懇願すれば復帰も夢ではないのに、文三は自尊心から毛嫌いしているその上司へ頭を下げることは
出来ないと考え、叔母や同僚の本田が上司に頭を下げろという言葉に耳を貸そうとしない。
やがて、叔母は仕事もしないで家にいる文三を煙たがるようになる。
ただ一人文三の味方になってくれるのは叔父夫婦の娘・お勢のみだった。
ところが、お勢との結婚を約束されていた文三だったが、その約束さえ怪しくなっていく。
お勢が本田と一緒に菊人形を見に行く時、文三は菊観を断り一人家で留守番をすることになる。
ところが、文三はお勢が本田と一緒にいることが気になってしょうがない。お勢たちが帰ってきたあと、叔母とお勢が
調子者だが愛想がよく話が面白い本田に一目置くようになる。
特に叔母が本田を評価したのは、本田が文三とは違い上司とうまくやって役所での仕事も順調にいっていることだった。
本田が頻繁に家にやってくるようになると、文三は本田とお勢が楽しく会話している姿を見聞きして嫉妬するようになる。
文三が大人気なくお勢に八つ当たりするようになると、今まで大目に見ていたお勢さえも文三を見捨て頼りがいのある
本田に興味を示すようになるのだった。
お勢に対して見かけの美しさと、親の過保護によって授けられた教育による知識の多さだけに目が行っていた文三だったが、
実際のお勢という女性が自分と思っていた女性とは違っているということに気づいていく。
淡い恋心を捨てきれず、自尊心を抑えながら叔母やお勢の嫌味を言われても我慢していたが、文三は最後の決断を下す。
お勢に告白して本心を尋ね、もし自分のことを嫌いになってしまったのであったら家を出て行く決心をする。
(2006.9.8/A)
二葉亭四迷(1864-1909)
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『欧洲小説 西洋梅暦 一名 恋情月の叢雲』(森知齋・福田直彦合訳/明治20年10月)
グールドンジェヌイヤック著とあるが、詳細不明。
また、原題についても不明だが、明治20年4月16日の官報に以下のような記載がある。
(レビュー未/以下は官報<第一一三六号 明治二十年四月十六日>より抜粋)
明治二十年四月十四日 内務省衛生局
○版権免許及返納書目広告
西暦一千八百八十一年佛国巴里刊行
題名ロンム、アウ、ドウー、フアンム
玉石情話 西洋梅暦 一名雙婦男
中本一冊
著 佛国グールドン、ジエヌイヤツク氏
訳 森知齋 福田直彦
出版 内澤安二良 東京
ロンム、アウ、ドウー、フアンム→L'homme aux deux femmes ?
森知齋( - )
福田直彦( - )
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『西洋 仙郷奇談』(井上寛一訳・矢野龍渓補/明治29年5月)
フランス人作家による童話12編を集めたアンソロジー。
(レビュー未/以下は収録作品)
ヴィルヌーヴ夫人「奇因縁(美女と野獣)」
ミュラ伯爵夫人「妹背情(Perfect Love)」
ミュラ伯爵夫人「美王樹(Anguillete)」
シャルル・ペロー「碧鬚(青ひげ)」
シャルル・ペロー「睡美人(眠れる森の美女)」
シャルル・ペロー「燻娘(シンデレラ)」
シャルル・ペロー「猫君(長靴をはいた猫)」
シャルル・ペロー「母指(親指小僧)」
ボーモン夫人「巨鼻児(ヒヤシンス王子とうるわしの姫)」
ボーモン夫人「秘蔵王(シェリー王子の物語)」
ボーモン夫人「苦楽(寡婦とふたりの娘の寓話)」
ボーモン夫人「鬼若福若(ファタル王子とフォルチュネ王子の物語)」
井上寛一( - )
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『今戸心中』(広津柳浪/明治29年7月)
(レビュー未/以下は作品の冒頭)
一
太空(そら)は一片(ぺん)の雲も宿(とど)めないが黒味渡ッて、二十四日の月はまだ上らず、霊あるがごとき星のきらめきは、仰げば身も冽(しま)るほどである。不夜城を誇り顔の電気燈にも、霜枯れ三月(みつき)の淋(さび)しさは免(のが)れず、大門(おおもん)から水道尻(すいどうじり)まで、茶屋の二階に甲走(かんばし)ッた声のさざめきも聞えぬ。
明後日(あさッて)が初酉(はつとり)の十一月八日、今年はやや温暖(あたた)かく小袖(こそで)を三枚(みッつ)重襲(かさね)るほどにもないが、夜が深(ふ)けてはさすがに初冬の寒気(さむさ)が身に浸みる。
少時前(いまのさき)報(う)ッたのは、角海老(かどえび)の大時計の十二時である。京町には素見客(ひやかし)の影も跡を絶ち、角町(すみちょう)には夜を警(いまし)めの鉄棒(かなぼう)の音も聞える。里の市が流して行く笛の音が長く尻を引いて、張店(はりみせ)にもやや雑談(はなし)の途断(とぎ)れる時分となッた。
廊下には上草履(うわぞうり)の音がさびれ、台の物の遺骸(いがい)を今室(へや)の外へ出しているところもある。はるかの三階からは甲走ッた声で、喜助どん喜助どんと床番を呼んでいる。
「うるさいよ。あんまりしつこいじゃアないか。くさくさしッちまうよ」と、じれッたそうに廊下を急歩(いそい)で行くのは、当楼(ここ)の二枚目を張ッている吉里(よしざと)という娼妓(おいらん)である。
「そんなことを言ッてなさッちゃア困りますよ。ちょいとおいでなすッて下さい。花魁(おいらん)、困りますよ」と、吉里の後から追い縋(すが)ッたのはお熊(くま)という新造(しんぞう)。
吉里は二十二三にもなろうか、今が稼(かせ)ぎ盛りの年輩(としごろ)である。美人質(びじんだち)ではないが男好きのする丸顔で、しかもどこかに剣が見える。睨(にら)まれると凄(すご)いような、にッこりされると戦(ふる)いつきたいような、清(すず)しい可愛らしい重縁眼(ふたかわめ)が少し催涙(うるん)で、一の字眉(まゆ)を癪(しゃく)だというあんばいに釣(つ)り上げている。纈(くく)り腮(あご)をわざと突き出したほど上を仰(む)き、左の牙歯(いときりば)が上唇(うわくちびる)を噛(か)んでいるので、高い美しい鼻は高慢らしくも見える。懐手(ふところで)をして肩を揺すッて、昨日(きのう)あたりの島田髷(まげ)をがくりがくりとうなずかせ、今月(この)一日(にち)に更衣(うつりかえ)をしたばかりの裲襠(しかけ)の裾(すそ)に廊下を拭(ぬぐ)わせ、大跨(おおまた)にしかも急いで上草履を引き摺(ず)ッている。
この作品は「青空文庫」にて読むことができます。→「今戸心中」(広津柳浪)
広津柳浪(1861-1928)
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『金色夜叉』(尾崎紅葉/明治30年1月~明治35年5月)
両親が亡くなった後、父親が世話した縁で鴫沢家に居候する間寛一は娘の宮と結婚を約束されていた。
ところが、宮に富山銀行の跡取りとの見合いの話が舞い込んでくる。
宮の両親は自分たちの将来を考えて、宮と富山銀行の息子との見合いを承諾するのだった。
両親は間寛一に対して、宮が銀行家一族の中に入ることで皆が幸せになるのだからと宮との結婚を諦めさせ、
宮の結婚後にはお前にも留学をさせてあげるという約束をする。
宮以外を自分の妻として考えられない間寛一は学校を辞めて、鴫沢家を出て行くのだった。
裸一貫で飛び出た間寛一が身を寄せた先は高利貸しを営む鰐淵の家だった。
間寛一は宮とその両親たちに裏切られた腹いせと人間不信から、債務者に対して非人間的な取立てをするようになり、
やがて学生時代の友人に対しても同様の取立てをして非難されるようになる。
そんな生活を送っていたことから、ある日、間寛一は債務者と思われる数人の暴漢に襲われ大怪我を負うのだった。
さらに、何者かによって鰐淵邸が放火され鰐淵夫妻が死亡する。
体に障害を負いながらも、鰐淵の遺産を相続して高利貸しをしていたところ、
間寛一のことを想って結婚生活がうまくいっていなかった宮が神経症者のような面立ちで
間寛一のもとに現れるのだった。
過去に許されざる仕打ちをした相手に対して、完全に拒絶する間寛一だったが、
死をもってつぐなうからと許してくれと宮が小刀で自刃し血の大滴を垂らしている姿を見て
さすがの間寛一も許さざるをえなくなるのだった。
その後、宮は湖に向って歩いていき、間寛一もその後を追っていく。
間寛一が湖にたどり着くと、溺死体となった宮を発見するのだった。
その姿を見た間寛一は宮を背負い、入水自殺をして、そして死んだと思いきや
目覚めると、間寛一は夢を見ていたことを知る。
夢落ち。それはないでしょ尾崎さん。
と、思いきや続々編、新続編と話が続いていく。
朝日新聞の朝刊小説として大人気を博した『金色夜叉』。
後半部分は、会社の意向で連載を強引に続けたことが露骨に分かるストーリーは無理がありすぎる設定。
小説黎明期に出版された作品なので、小説ならではのディテールを凝るというよりは、
いかに一般大衆の気をひくような文を書くかということに特に重きを置いている感じがする。
まるで活劇を観ているかのような展開と、会話のやり取りが行われている。
(2006.9.8/A)
尾崎紅葉(1867-1903)
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
「高野聖」(泉鏡花/明治33年2月)
(レビュー未/以下は作品の冒頭)
第一
「参謀本部編纂の地図を又繰開(くりひら)いて見るでもなからう、と思つたけれども、余りの道ぢやから、手を触るさへ暑くるしい、旅の法衣(ころも)の袖をかゝげて、表紙を附けた折本(をりほん)になつてるのを引張り出した。
飛騨から信州へ越える深山(しんざん)の間道(かんだう)で、丁度(ちやうど)立休(たちやす)らはうといふ一本の樹立も無い、右も左も山ばかりぢや、手を伸ばすと達(とゞ)きさうな峯(みね)があると、其(そ)の峯へ峯が乗り巓(いたゞき)が被(かぶ)さつて、飛ぶ鳥も見えず、雲の形も見えぬ。
道と空との間に唯(たゞ)一人我(わし)ばかり、凡(およ)そ正午と覚しい極熱(ごくねつ)の太陽の色も白いほどに冴え返つた光線を、深々と頂いた一重の檜笠(ひのきがさ)に凌(しの)いで、恁(か)う図面を見た。」
旅僧(たびそう)は然(さ)ういつて、握拳(にぎりこぶし)を両方枕に乗せ、其(それ)で額を支へながら俯向(うつむ)いた。
道連(みちづれ)になつた上人(しやうにん)は、名古屋から此(こ)の越前敦賀の旅籠屋(はたごや)に来て、今しがた枕に就いた時まで、私が知つてる限り余り仰向けになつたことのない、詰(つま)り傲然(がうぜん)として物を見ない質(たち)の人物である。
一体東海道掛川(かけがは)の宿(しゆく)から同じ汽車に乗り組んだと覚えて居る、腰掛の隅に頭(かうべ)を垂れて、死灰(しくわい)の如く控へたから別段目にも留まらなかつた。
尾張(をはり)の停車場(ステーシヨン)で他(た)の乗組員は言合(いひあ)はせたやうに、不残(のこらず)下りたので、函(はこ)の中には唯(たゞ)上人(しやうにん)と私と二人になつた。
此(こ)の汽車は新橋を昨夜九時半に発(た)つて、今夕(こんせき)敦賀に入らうといふ、名古屋では正午(ひる)だつたから、飯に一折(ひとをり)の鮨(すし)を買つた。旅僧(たびそう)も私と同(おなじ)く其(そ)の鮨を求めたのであるが、蓋を開けると、ばら/\と海苔(のり)が懸(かゝ)つた、五目飯(ちらし)の下等(かとう)なので。
(やあ、人参(にんじん)と干瓢(かんぺう)ばかりだ、)と踈匆(そゝ)ツかしく絶叫した、私の顔を見て旅僧(たびそう)は耐(こら)へ兼ねたものと見える、吃々(くつ/\)と笑ひ出した、固(もと)より二人ばかりなり、知己(ちかづき)にはそれから成つたのだが、聞けば之(これ)から越前(ゑちぜん)へ行つて、派は違ふが永平寺(えいへいじ)に訪ねるものがある、但(たゞ)し敦賀(つるが)に一泊とのこと。
若狭(わかさ)へ帰省する私もおなじ処(ところ)で泊(とま)らねばならないのであるから、其処(そこ)で同行の約束が出来た。
この作品は「青空文庫」にて読むことができます。→「高野聖」(泉鏡花)
泉鏡花(1873-1939)
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『麗子夫人』(小栗風葉/明治39年3月)
(レビュー未)
本作の文体、文章表現が、明治小説の文体の例として取り上げられている。
明治初期の作品で用いられた文体は、私たちにはとっつきにくいところがあるが、この頃になると、現代のそれと表現が近しい。
(以下、海賀変哲編「新式小説辞典」<博文館/明治42年5月>女子・貴婦人の項より)
體(たい)を欄干(らんかん)に靠(もた)せて、斜(なゝめ)に映(えい)ずる庭木(にはき)の綠(みどり)の影(かげ)を半身(はんしん)に浴(あ)びながら、夏(なつ)の日(ひ)のキラ/\しい光(ひかり)に眞面(まとも)に打向(うちむか)つた其顔(そのかほ)──活々(いき/\)とした澤々(つや/\)しい、其(そ)の顏(かほ)は、美(うつく)しいと云(い)ふよりは寧(むし)ろ神々(かう/\)しい、愛(あい)らしいと云(い)ふよりは寧(むし)ろ厳(いかめ)しい、彼(か)の明放(あけはな)しの、葉出(はで)な、男好(をとこず)きの為(す)る嬌(なま)めかしい所(ところ)は無(な)いが、飽(あ)くまでも氣高(けだか)く上品(じやうひん)で居(ゐ)て、其(そ)れで何處(どこ)か情(じやう)の深(ふか)さうな一目(ひとめ)見(み)ると忘(わす)られぬ妙味(めうみ)を持(も)つた顔容(かほつき)。
小栗風葉(1875-1926)
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
「金貨」(森鴎外/明治42年9月)
左官屋の八はぼろ着を纏い、千駄ヶ谷の停車場の改札の前で何をするともなく突っ立っていた。
改札から三人連の軍人が出てくる。一番先頭を歩く軍人は襟章からして大佐か中佐と思われた。
八は無意識に三人連の後をつけるようにして歩いていくのだった。
三人連は冠木門の邸宅に入っていく。
先頭を歩く一番偉そうな人物がこの邸宅の主人だった。
八は庭の竹林に忍び込んで様子を伺っていると、三人連はビールを飲みながら碁を始める。
雨が降ってきて八の着ている半纏はかなり濡れていたが、八は意に介さなかった。
しばらくすると、八は尿意を催したので仕方なく椿の木の下に隠れてひっそりするのだった。
三人連はとうとうビールを飲み干し、次には主人がコニャックを取り出してお湯割にして飲みだす。
やがて、碁の勝負も終わり寝静まる。
寝入ったのを見計らって、八は三人連れが碁をしていた部屋に忍び込む。
八はあまりにも咽喉が渇いていたため、ビールの瓶を傾けるが中には一滴も残っていない。
ところが、コニャックはまだかなり残っていた。
八はコニャックを割らないでぐっと飲む。
アルコール度が高く咽喉がやけるような気がしたがその味わいに幻惑し、
八はコニャックの瓶を何度も傾ける。
そして、いつしか八は夢の中に入り込んでいくのだった。
(2006.8.12/A)
森鴎外(1862-1922)
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『青年』(森鴎外/明治43年3月~明治44年8月)
小説家を目指して上京した文学青年の小泉純一は、文士を尋ねて文学との関わり方を探るなか、
裕福で恵まれた家庭に育った自分には行動力や小説の題材となる経験がないと意識するようになる。
有楽座にイプセンの演劇を観に行き、そこで坂井未亡人と知り合う。未亡人は夫と同郷の小泉に対して親近感を示し
また夫が学者だったこともあり家には沢山の書物を所蔵しているので、小泉に書物を貸そうと申し出る。
小泉は坂井未亡人宅を訪問しラシーヌの本を借りた時、夫人から箱根へ行くので遊びに来ないかと誘われるのだった。
小泉は色々な集まりに参加するが、自分と他人との距離感に寂しさを募らせ、坂井未亡人が滞在している箱根に向うことを決心する。
ところが、箱根に到着すると宿は見つからないので仕方なく警察官に紹介してもらった宿は不潔で寝そべると服が
汚れてしまうような所だったりと、ついてないなと思っていたところ、小泉は坂井未亡人が頑強な体格の男と二人で
歩いている所に遭遇する。
坂井未亡人は気兼ねする小泉に対して躊躇することなく声をかけた。
坂井未亡人と一緒にいる40代らしき男は小泉も名前を知っている有名な画家であった。
小泉は嫉妬に駆られながらも、男と未亡人の関係を疑りながらも僅かな淡い望みを抱いて坂井未亡人の泊まる宿を伺う。
しかし、小泉がそこで知ったのは本人の願望とは裏腹に、二人の親密な関係をまざまざと見せ付けられるばかりだった。
結局、小泉は箱根を去っていく。
主人公の独白というスタイルで書かれていて、主人公の行動原理はいかにも文学青年が思いつきそうな
小説を書くことに直接関係するようなものーいわゆる西洋哲学だったり欧州文学などの話題を見たり聞くことのみ。
恋愛や友情に到るかもしれない人間関係には極力深入りしないように心がけている。
とにかく主人公は他人と一定の距離を保ちあくまで観察者としての立場を貫くのだ。
その結果、この小説で描かれている登場人物や場所、会話などこの小説に描かれている全ての事象と
主人公の意識との間に大きな距離感が生じてしまっている 。
ただ同じようなやりとりが永遠と繰り返されていて気がしてならない。
(2006.8.28/A)
森鴎外(1862-1922)
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
「濁った頭」(志賀直哉/明治44年4月)
“(自分はいつも余り物を云わない津田君の今晩の調子に驚かされた。そして二年間も癲狂院で絶えず襲われていたと云うこの人の恐ろしい夢を……然し津田君は単刀直入に聞いてくれと云って語り出した。)”
物語はそんな一節から始まる。いわば津田という男の半生の告白だ。
小説家になろうと思っていた少年時代。そして17歳からキリスト教徒として生きた7年間。
母方の親類で遊びかたがた彼の家に手伝いにやってきていた、彼より4つ年上でお夏という名の女性との恋…。
彼は青春時代をどう生き、何が彼を癲狂院に向かわせたのか。絶え間なく葛藤を繰り返す彼の苦悩の日々が描かれる。
志賀直哉の作品では、父への反抗心がテーマとなることがしばしばあるが、この作品でもその一面が垣間見られる。
この作品を読んでいると、何故かふと夢野久作の作品を連想してしまった。
(2006.5.6/菅井ジエラ)
本誌内企画“志賀直哉を読む”より再掲。
志賀直哉(1883-1971)
詳細は本誌内企画“志賀直哉を読む”ページをご覧ください。
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
「樹蔭(樹陰)」(松本泰/明治44年10月)
慶応義塾大学在学中、『三田文学』に発表。
(レビュー未)
『天鵞絨』(籾山書店/大正2年)所収
「築地の家」「樹蔭」「U君の話」「W倶楽部」「ウヰンタア」「温室より」「玩具(おもちや)」「けいちやん会議」「P君の批評」「一週間の夢」「墓まゐり」「暗き家」
松本泰(1887-1939)
東京生まれ。本名は泰三(たいぞう)。イギリス遊学中に伊藤恵子(翻訳家の松本恵子)と結婚。
主に探偵小説の分野で数々の作品を残している。
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
【明治45年(1912年)に起こったできごと】
・吉本興業創業(4月1日)
・タイタニック号が北大西洋で氷山に衝突し、沈没(4月14日)
・明治天皇が崩御。元号を大正に改元(7月30日)
●この年に生まれた著名人
源氏鶏太(日本の小説家/~昭和60年)
●この年に亡くなった著名人
石川啄木(日本の歌人・詩人/明治19年~)
アンリ・ポアンカレ(フランスの数学者/1854年~)
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『彼岸過迄』(夏目漱石/明治45年1月~4月)
大学を卒業した後に職につかずフラフラとしている敬太郎は、同じ宿に下宿する森本という男と酒を飲み交わす。
森本という男は酒を飲んで酔ってくると、年上なことをいいことに兄貴然と自分の武勇伝などを絡めて
人生論を垂れるのだった。森本は偉そうな事を言っておきながら、仕舞いには自分には学歴がないからと不貞腐れるような男だったので
尊敬には値しなかったが、人生経験の乏しい敬太郎は自分の経験のなさを実感することになる。
ところが、数日後に森本は突然夜逃げするような形で下宿先からいなくなってしまう。大家は森本が半月近く家賃を
払っていなかったので相当頭にきている。それから、しばらくして敬太郎のもとに森本からの手紙が届くのだった。
森本はどうやら大陸に渡ったらしく、上海で仕事にありついたと書き記してある。そして、玄関脇に置いたままになっている
洋杖を敬太郎に譲るということが記されていた。森本がいなくなった後、下宿先の玄関脇に置きざりにされていた。
洋杖の先には蛇の彫刻が彫られている。森本自らが彫ったものだったが悪くはない仕立てであった。
敬太郎は友人の家柄の良い須永に仕事を斡旋してもらいにいくと、叔父の田口という男を紹介される。
田口に会いに行く前に、敬太郎は文銭占いをするお婆さんに占ってもらうのだが、
その占い師のおばあさんは敬太郎の未来をこう予言する。
「貴方は自分のような又は他人のような、長いような又は短い様な、出るような又は入るようなものを持って
いらっしゃるから、今度事件が起こったらそれを忘れないようにしなさい。そうすればうまく行きます。」
敬太郎はこの怪しい占いを信じてみることに決め、占い師の言う長いようで短いようなものとは
森本が置いていった洋杖のことだと一人合点し、どこへ行くにも必ず洋杖を持ち歩くのだった。
敬太郎は須永の叔父の田口に、また別の叔父の松本を探偵することを命じられたりするなど
須永の親類と親交を深めていき、やがて友人須永の信じがたい過去を知ることになる。
それは、森本の酩酊しながらの自慢話とは違い、人生の真実に触れるような告白だった。
(2006.8.28/A)
夏目漱石(1867-1916)
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
『哀花熱花』(兒玉傅八/明治45年5月)
(レビュー未)
『哀花熱花』(春陽堂・現代文芸叢書:第11編/明治45年5月)所収
「芸人の悲哀」「泥船」「久世山の夏草」「二階の下」「絶望」「東京の女と柳」「美人像」「鳶」「苗売」「夏の隅田川」「網納屋」「舟中の少年」「顔」「橋」「汚れ身」「情熱」「風濤の別れ」「闇黒」「幻影」「秋風語」「鶏」「蝉の音楽」「女優」「煙草入」「南国の女」「鰯雲」「女乞食」「図書館の日」「卓の前」「犬」「鷺」「雷鳴の夜」「鎌倉の半日」「病院前」「九十九湾の一夜」
児玉(兒玉)花外(傅八)(1874-1943)
旧長州藩士、児玉精斎の長男。明治36年に出した『社会主義詩集』は、国内の安寧秩序を害するとして発売禁止に。日本で初めて発禁処分を受けた詩集となった。
ページの先頭にもどる
|
|
|
|
本企画の制作にあたっては、以下のHPサイトを参照させていただいております(順不同)。
青空文庫 Aozora Bunko
(https://www.aozora.gr.jp/)
国立国会図書館デジタルコレクション
(https://dl.ndl.go.jp/)
|